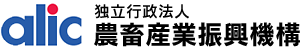ホーム > 砂糖 > お砂糖豆知識 > 内外の伝統的な砂糖製造法(5)
最終更新日:2011年11月9日
内外の伝統的な砂糖製造法(5)〜吉宗時代のさとうきびのその後〜
2011年11月
昭和女子大学国際文化研究所 客員研究員 荒尾 美代
前号では、八代将軍吉宗が砂糖の国産化を目指したため、薩摩藩士が浜御殿で、さとうきびの栽培を実践したことを書いた。
では、そのさとうきびは、どうなったのかが今回のテーマである。
享保年間には、砂糖のみならずさまざまな薬種の国産化を図った幕府は、享保5年に駒場薬園の新設、享保6年に小石川薬園の拡大、そして、享保7年に江戸近郊の千葉県へも、それらを試植・栽培・増殖のための薬園を造設した。今回の舞台は、千葉県の薬園である。
なんと、当時の幕府は、千葉県に30万坪の薬園を作ったのである。小石川薬園が4万4800坪なので、約6.7倍の広さである。この薬園の管理者の一人は、前号でも何度か名前が出てきた丹羽正伯であった。
丹羽正伯は、元々は紀州の医者の出であったが、享保3年に江戸に出て町医者をする傍ら、享保5年から、幕府の採薬御用(採薬使)として各地へ赴いて、薬となる有用な動植物の調査を行った。そして、幕府の奥医師並として30人扶持を与えられて医官として登用されたのが享保7年4月1日のこと、その3日後の4月4日には、下総国千葉郡小金原滝野台(現在の船橋市薬園台)の薬園15万坪の管理・運営を任されている。そして、もう一人、同時にこの薬園の別の15万坪を任されたのは、江戸の薬種商であった桐山太右衛門という人物であった。享保5年5月には、日光・箱根・信州木曽方面へ、享保6年3月には山城・丹波・但馬・丹後・若狭・飛騨・近江へ、同年7月には陸奥・出羽・常陸へ、何度か正伯に同道して、採薬に赴いている。
幕府は享保6年から設立準備を進めていた国産薬種の普及を目的とした和薬の検査機関である和薬改会所を、正伯、太右衛門に滝野台薬園の管理・運営を任せた直後の享保7年6月に江戸に開設した。
薬草といっても、雑草とどう見分けることができるか。その辺の草を「薬草」といっても分かる人が少ない時代のことである。また、動物や鉱物にも薬種になったものがあったが、同様に相当な知識と鑑識眼がなければ、偽薬を見分けることができない。だからこそ、マガイモノが流通しないように、和薬の仕入れを独占して、統括・チェックする機関である和薬改会所の必要があったのだ。
その和薬改会所は、江戸の24の薬種問屋と、問屋に加えられた太右衛門が運営することになった。統括者が正伯で、責任者が太右衛門である。正伯は、太右衛門のことを、「近年御用ニ付国々入いたし、薬草見覚、其上生薬・おし葉共有之間」と称している。太右衛門は秀でた鑑識眼を持っていたことを窺わせる言葉である。このように、正伯と太右衛門は、この時代を担う名コンビといっていいだろう。
この正伯と太右衛門が管理・運営する下総国の薬園に、享保16年に浜御殿のさとうきびを移植するということになったのである。
浜御殿にさとうきびを植え付けたのが享保12年のこと。享保14年には栽培したさとうきびから砂糖の試作にこぎつけた模様で、その2年後の享保16年には、黒砂糖が出来るに至った。
黒砂糖を試作するには、さとうきびの茎が大量に必要である。さとうきびの栽培が順調にすすみ、「種」を殖やすことに成功して、黒砂糖を試作製造するまでにさとうきび栽培が、江戸の地で一応成功したものと考えられる。
浜御殿のさとうきびの「種」を下賜されることになった正伯は、浜御殿の最高責任者の奉行、石丸定右衛門から書付を受け取った。これには、栽培法を記した「砂糖秬(きび)作り様」、砂糖の作り方を記した「同拵(こしらえ)様」、さとうきびの茎を種としてその保存法を記した「同苗囲(なえかこい)様」が記されていた。いわゆるマニュアルである。幕府は、中国の商船から砂糖製造法の書付を提出させてもいたが、これは実際に浜御殿で試植された方法とみていいだろう。
その栽培法は、
1.畑を耕し、土を細かくして、畦巾を3尺余り、間も3尺ほどにして土が3寸ほどかかるように植える。ただし、「種」となるさとうきびの茎は、1節に芽が一つならば、芽が上になるように、2節に芽が二つあれば、芽が脇になるように植える。
2.土の上に芽が4〜5寸伸び出たら、段々伸びるように、根の脇に土を寄せて、土の中の節々から芽が出て株が多く出るようにする。
3.芽が4〜5寸程伸び出てから、土用前までに3度ほど、さとうきびの廻りを深さ2寸位堀出し、肥(こえ)を入れる。干鰯(ほしか)などを水に入れてかけてもよい。もちろん、土地によるさとうきびの出来の様子次第で施肥を調節する。
砂糖の作り方は、
1.さとうきびの実入り次第で、10月初めから霜がかからない間に刈り取って絞るのがよい。
2.土際よりさとうきびを刈り取り、先端の実入りが良くないところは切る。
3.枌葉(そぎは)を取り、節々をこそげ、よく洗って水気が残らないように拭いて、轆轤(ろくろ)で絞り、ジュースを釜に入れて煎じる。
4.釜は2つでも3つでも、ジュースが煮詰まるにしたがって、釜1つに移し入れ、だんだん沸いてくるようにする。
5.初めは火を強くし、煎じ詰まるにしたがって火を細くする。
6.煎じ詰まって、アワが大きく煮上がった時、ジュース1升につき石灰1分2厘程の積もりで入れ火を細くし、杓子でかき回し、アワの穴が凹みのように煮上がった時、茶碗などに水を入れ、その中に濃縮糖液を少し入れてみて、水の中で玉になった時に、桶に移して冷ます。
これは、黒砂糖の製法とみていいだろう。
最後は、「種」にするさとうきびの茎の保存法である。
1.霜が降りないうちに、切山でも土手でも南向きの日当たりの良いところに、横に穴を掘り、穴の中の下にも脇にも藁(わら)や籾糠(もみぬか)を置き、さとうきびの茎を1本ずつ並べて置き、また藁や糠などを置き、同様にだんだん並べ、穴の口は土で堅く塞ぎ、雨水を通さないように上へも肥などを掛けておく。
2.3月上旬にこれを取り出し、芽の勢いによって1節または2節充てに切り植え付ける。
しかし、最初から下総国の薬園に浜御殿のさとうきびを移植するという話ではなかった。
そもそも、桐山三了という人物が、浜御殿のさとうきびを移植して、世に広めるように幕府から言い渡されたのだが、三了は、植え付ける土地を持っていないので、太右衛門が持っている下総国の薬園に植え付けることになった。正伯と各地へ採薬しに出かけた太右衛門は、享保11年3月20日に亡くなっており、「息子の桐山太右衛門」が薬園を引き継いだとみられ、さとうきび移植の担当となった。同じ名前を代々継承するのでややこしいのであるが、享保時代には、親の桐山太右衛門と子である桐山太右衛門がいたのである。
この薬園は、現在の千葉県船橋市の新京成線の薬園台駅付近にあった。駅名が「薬園台」というのは、かつて薬園があったことから名づけられている。
ここに、親である太右衛門の墓がある。(写真1)
では、そのさとうきびは、どうなったのかが今回のテーマである。
享保年間には、砂糖のみならずさまざまな薬種の国産化を図った幕府は、享保5年に駒場薬園の新設、享保6年に小石川薬園の拡大、そして、享保7年に江戸近郊の千葉県へも、それらを試植・栽培・増殖のための薬園を造設した。今回の舞台は、千葉県の薬園である。
なんと、当時の幕府は、千葉県に30万坪の薬園を作ったのである。小石川薬園が4万4800坪なので、約6.7倍の広さである。この薬園の管理者の一人は、前号でも何度か名前が出てきた丹羽正伯であった。
丹羽正伯は、元々は紀州の医者の出であったが、享保3年に江戸に出て町医者をする傍ら、享保5年から、幕府の採薬御用(採薬使)として各地へ赴いて、薬となる有用な動植物の調査を行った。そして、幕府の奥医師並として30人扶持を与えられて医官として登用されたのが享保7年4月1日のこと、その3日後の4月4日には、下総国千葉郡小金原滝野台(現在の船橋市薬園台)の薬園15万坪の管理・運営を任されている。そして、もう一人、同時にこの薬園の別の15万坪を任されたのは、江戸の薬種商であった桐山太右衛門という人物であった。享保5年5月には、日光・箱根・信州木曽方面へ、享保6年3月には山城・丹波・但馬・丹後・若狭・飛騨・近江へ、同年7月には陸奥・出羽・常陸へ、何度か正伯に同道して、採薬に赴いている。
幕府は享保6年から設立準備を進めていた国産薬種の普及を目的とした和薬の検査機関である和薬改会所を、正伯、太右衛門に滝野台薬園の管理・運営を任せた直後の享保7年6月に江戸に開設した。
薬草といっても、雑草とどう見分けることができるか。その辺の草を「薬草」といっても分かる人が少ない時代のことである。また、動物や鉱物にも薬種になったものがあったが、同様に相当な知識と鑑識眼がなければ、偽薬を見分けることができない。だからこそ、マガイモノが流通しないように、和薬の仕入れを独占して、統括・チェックする機関である和薬改会所の必要があったのだ。
その和薬改会所は、江戸の24の薬種問屋と、問屋に加えられた太右衛門が運営することになった。統括者が正伯で、責任者が太右衛門である。正伯は、太右衛門のことを、「近年御用ニ付国々入いたし、薬草見覚、其上生薬・おし葉共有之間」と称している。太右衛門は秀でた鑑識眼を持っていたことを窺わせる言葉である。このように、正伯と太右衛門は、この時代を担う名コンビといっていいだろう。
この正伯と太右衛門が管理・運営する下総国の薬園に、享保16年に浜御殿のさとうきびを移植するということになったのである。
浜御殿にさとうきびを植え付けたのが享保12年のこと。享保14年には栽培したさとうきびから砂糖の試作にこぎつけた模様で、その2年後の享保16年には、黒砂糖が出来るに至った。
黒砂糖を試作するには、さとうきびの茎が大量に必要である。さとうきびの栽培が順調にすすみ、「種」を殖やすことに成功して、黒砂糖を試作製造するまでにさとうきび栽培が、江戸の地で一応成功したものと考えられる。
浜御殿のさとうきびの「種」を下賜されることになった正伯は、浜御殿の最高責任者の奉行、石丸定右衛門から書付を受け取った。これには、栽培法を記した「砂糖秬(きび)作り様」、砂糖の作り方を記した「同拵(こしらえ)様」、さとうきびの茎を種としてその保存法を記した「同苗囲(なえかこい)様」が記されていた。いわゆるマニュアルである。幕府は、中国の商船から砂糖製造法の書付を提出させてもいたが、これは実際に浜御殿で試植された方法とみていいだろう。
その栽培法は、
1.畑を耕し、土を細かくして、畦巾を3尺余り、間も3尺ほどにして土が3寸ほどかかるように植える。ただし、「種」となるさとうきびの茎は、1節に芽が一つならば、芽が上になるように、2節に芽が二つあれば、芽が脇になるように植える。
2.土の上に芽が4〜5寸伸び出たら、段々伸びるように、根の脇に土を寄せて、土の中の節々から芽が出て株が多く出るようにする。
3.芽が4〜5寸程伸び出てから、土用前までに3度ほど、さとうきびの廻りを深さ2寸位堀出し、肥(こえ)を入れる。干鰯(ほしか)などを水に入れてかけてもよい。もちろん、土地によるさとうきびの出来の様子次第で施肥を調節する。
砂糖の作り方は、
1.さとうきびの実入り次第で、10月初めから霜がかからない間に刈り取って絞るのがよい。
2.土際よりさとうきびを刈り取り、先端の実入りが良くないところは切る。
3.枌葉(そぎは)を取り、節々をこそげ、よく洗って水気が残らないように拭いて、轆轤(ろくろ)で絞り、ジュースを釜に入れて煎じる。
4.釜は2つでも3つでも、ジュースが煮詰まるにしたがって、釜1つに移し入れ、だんだん沸いてくるようにする。
5.初めは火を強くし、煎じ詰まるにしたがって火を細くする。
6.煎じ詰まって、アワが大きく煮上がった時、ジュース1升につき石灰1分2厘程の積もりで入れ火を細くし、杓子でかき回し、アワの穴が凹みのように煮上がった時、茶碗などに水を入れ、その中に濃縮糖液を少し入れてみて、水の中で玉になった時に、桶に移して冷ます。
これは、黒砂糖の製法とみていいだろう。
最後は、「種」にするさとうきびの茎の保存法である。
1.霜が降りないうちに、切山でも土手でも南向きの日当たりの良いところに、横に穴を掘り、穴の中の下にも脇にも藁(わら)や籾糠(もみぬか)を置き、さとうきびの茎を1本ずつ並べて置き、また藁や糠などを置き、同様にだんだん並べ、穴の口は土で堅く塞ぎ、雨水を通さないように上へも肥などを掛けておく。
2.3月上旬にこれを取り出し、芽の勢いによって1節または2節充てに切り植え付ける。
しかし、最初から下総国の薬園に浜御殿のさとうきびを移植するという話ではなかった。
そもそも、桐山三了という人物が、浜御殿のさとうきびを移植して、世に広めるように幕府から言い渡されたのだが、三了は、植え付ける土地を持っていないので、太右衛門が持っている下総国の薬園に植え付けることになった。正伯と各地へ採薬しに出かけた太右衛門は、享保11年3月20日に亡くなっており、「息子の桐山太右衛門」が薬園を引き継いだとみられ、さとうきび移植の担当となった。同じ名前を代々継承するのでややこしいのであるが、享保時代には、親の桐山太右衛門と子である桐山太右衛門がいたのである。
この薬園は、現在の千葉県船橋市の新京成線の薬園台駅付近にあった。駅名が「薬園台」というのは、かつて薬園があったことから名づけられている。
ここに、親である太右衛門の墓がある。(写真1)

墓に記されているように、享保11年3月20日に、親の太右衛門は、50歳で亡くなっている。戒名に「観草」という字が入っているのが、薬草に詳しかった太右衛門らしい。墓石の別の側面には(写真2)、

と、親の太右衛門が亡くなった年の11月に、幕府から、浜御殿のさとうきびを世に広めるために白羽の矢が立った三了が、桐山一族とみられる墓を建立したことが刻まれている。
時代は下るが、薬種店主として桐山三了の名が、文政7(1824)年刊行の『江戸買物独案内』の中にみえる。『江戸買物独案内』は、江戸市内の地理に不案内の人のための、ショッピングガイドブックの類である。三了は、見開き2頁に渡って薬種店の広告を載せている。
以下は、その頁である。(写真3)(写真4)
時代は下るが、薬種店主として桐山三了の名が、文政7(1824)年刊行の『江戸買物独案内』の中にみえる。『江戸買物独案内』は、江戸市内の地理に不案内の人のための、ショッピングガイドブックの類である。三了は、見開き2頁に渡って薬種店の広告を載せている。
以下は、その頁である。(写真3)(写真4)
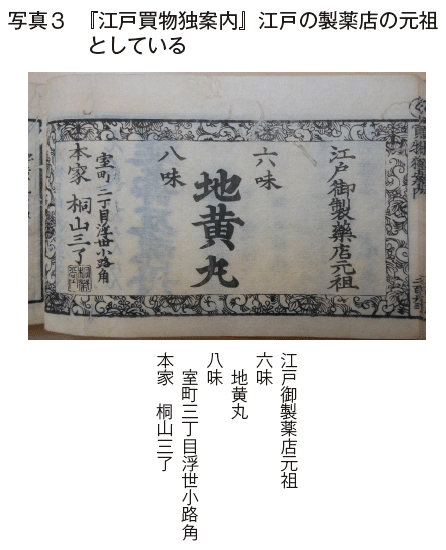
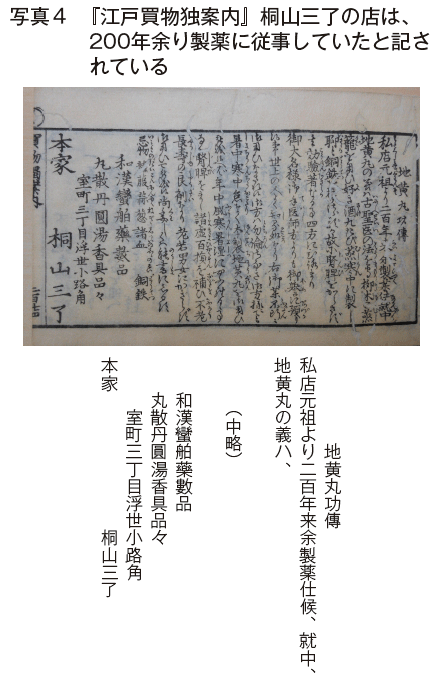
これによれば、三了の店は、江戸の製薬店の元祖であり、200年以上前から製薬を行っていたとしている。
今は、薬園の面影は全くないが、さとうきびを増殖して、普及させる黎明期を歩んだこの地に立つと、感慨深いものがある。
今は、薬園の面影は全くないが、さとうきびを増殖して、普及させる黎明期を歩んだこの地に立つと、感慨深いものがある。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713