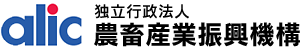最終更新日:2013年9月10日
サトウキビ産業の進む道〜南西諸島の現在と将来に向けて〜
2013年9月
サトウキビコンサルタント 杉本 明
はじめに
日本のサトウキビ産業について、後継者の不足、生産量の減少が語られて久しく、今はTPP交渉後における産業存続への危惧が語られることが多い。一方、積年の課題である低収量には改善の色が見えず、それどころか平成23/24年期には、沖縄・奄美地域を深刻な不作が襲っている。異常な気象故と多くの関係者は話したが、昨期もまた、全地域が不作に見舞われた。2年連続して「異常」があるのだとしたら、それをも前提とした生産技術が必要であろう。対応策として適期管理が打ち出されることが多いが、高齢化した担い手、生活維持故に必要となる複合型の作業構造の中で、適期管理は実行できるであろうか。一つ大きな気懸かりである。そしてもう一つ、忘れてならないのは、連続する不作への対応が技術の本質的な課題なのかとする問いである。サトウキビ産業は南西諸島の島々の基幹的経済活動としてある。基幹的経済活動の技術課題という面からは、連続する不作への直接の対応策以上に、サトウキビの地域産業としての存在意義を問う必要が大きいのではないだろうか。地域社会を支える基幹産業として、多くの人がそこから生活の糧を得ることのできる高い人口涵養力、はたしてそれを満たす高い価値創出をしているだろうか。それを問い直すことが不作に悩む今日にあってもなお最重要であると思う。高い価値創出とその持続、本稿ではこのことを主題に技術的な可能性を探ろうと思う。
1.世界のサトウキビ日本のサトウキビ
(1)サトウキビ産業の規模(サトウキビ畑そして製糖工場)
ブラジルは世界一のサトウキビ大国、生産量は7億トンを上回り(2011年)、半分で砂糖を、残る半分でエタノールを生産する。世界一の砂糖輸出国でもある。広大なサトウキビ圃場、自営農場を中心とする高度に管理された生産(収穫順路や工場への運搬経路はGPS管理で効率化されているという)、単位収量も高い。2位インド、3位中国、4位がタイ{およそ1億トン(2012年、7.3t/10a)}である。
豪州は大規模機械化管理で名高い。生産量も世界第8位である。収量は10アール当たり8トン程度で高い。株出しの継続回数も日本より遥かに多く、5〜6回は続けている。
日本の生産量はサトウキビも砂糖も世界で40数番目、ブラジルなどを基準にして棒グラフを作ると、日本を示す棒は目に入らない。製糖工場の規模の評価には、1日当たり原料処理量が分かりやすいが、タイには公称4万トンの工場がある。先日訪ねたブラジルの工場は2万4000トン、石垣島の生産量なら4日、種子島の生産量でも7日程度で終わってしまう。操業日数は215日程度ということであった。日本は1日当たり平均1,000トン、最も大きな工場で同2,100トンである。操業日数も種子島以外では80日程度で短い。生産規模は、労働生産性の高低などを介してコストの行方を決める重要な要素であるが、上記のように、日本の生産規模は圃場も工場も世界とは比較にならないほど小さい。
(2)南西諸島のサトウキビ産業において労賃、単位収量が示すこと
日本のサトウキビ産業のもう一つの特徴、これは大切なこと、良いことであるが、労賃単価が高いことである。日本は生活水準が高く、基本的には海外のサトウキビ生産国と比べ労賃単価が高い。サトウキビや砂糖のコストとしてのそれも必然的に高くなる。購買力を増し、生活を豊かにするはずの賃金の高さは、産業の競争力という面からは辛い側面として立ち現れることが多い。コスト低減のために人件費総額を減らすことも論理的には可能である。しかし、人件費総額が少ないことは、多数の人がその産業に関わることができないこと、すなわち、産業の人口涵養力が低いことを意味し、地域の基幹産業としては致命的な欠陥を内部に宿すことに他ならない。
生産規模が大きいことがコスト低減の大きな要因であることを先に述べた。労賃単価が低いこともまた同様な意味を持つが、二つとも日本のサトウキビ産業にはない。ならば、規模の拡大や人件費割合の縮小を何処に求めたら良いのだろうか。圃場の面的拡大が不可能だとしたら、空間的・時間的(単位収量) 拡大はどうであろうか。単位収量が高いこと、すなわち土地利用の高度化が一つの道である。同一重量の作物からできる限り多くの価値を取り出すこと、すなわち作物の高度利用も重要な道である。単位収量の世界平均は株出しを含め10アール当たり7トン程度である。株出しは大規模栽培が特徴のブラジル、オーストラリアなどでも5回程度は継続される。日本の場合、株出しの回数は0〜2回のところが多く、収量はおおむね10アール当たり6トンである。生産規模が小さく株出し回数が少ない割には低すぎる収量である。残された道は同じ重量のサトウキビからできる限り大きな価値を生み出すことであるが、現在は大部分の工場が砂糖だけを商品としている。世界の主要国では、砂糖、エタノール、電力が常識的な商品構成である。日本における原料当たり価値創出は世界的には低水準であると言わざるを得ない。
地域の基幹的経済活動としての日本のサトウキビ産業が少しでも自立性を高めるには、面的規模の小ささ、さらには労賃水準の高さを補うに足る単位収量と商品売り上げ量の向上が必要であるが、技術的にはそれは何を意味するのだろうか。地域の農業という立場で考えてみたい。地域の特徴を知ることからそれが始まると思う。
ブラジルは世界一のサトウキビ大国、生産量は7億トンを上回り(2011年)、半分で砂糖を、残る半分でエタノールを生産する。世界一の砂糖輸出国でもある。広大なサトウキビ圃場、自営農場を中心とする高度に管理された生産(収穫順路や工場への運搬経路はGPS管理で効率化されているという)、単位収量も高い。2位インド、3位中国、4位がタイ{およそ1億トン(2012年、7.3t/10a)}である。
豪州は大規模機械化管理で名高い。生産量も世界第8位である。収量は10アール当たり8トン程度で高い。株出しの継続回数も日本より遥かに多く、5〜6回は続けている。
日本の生産量はサトウキビも砂糖も世界で40数番目、ブラジルなどを基準にして棒グラフを作ると、日本を示す棒は目に入らない。製糖工場の規模の評価には、1日当たり原料処理量が分かりやすいが、タイには公称4万トンの工場がある。先日訪ねたブラジルの工場は2万4000トン、石垣島の生産量なら4日、種子島の生産量でも7日程度で終わってしまう。操業日数は215日程度ということであった。日本は1日当たり平均1,000トン、最も大きな工場で同2,100トンである。操業日数も種子島以外では80日程度で短い。生産規模は、労働生産性の高低などを介してコストの行方を決める重要な要素であるが、上記のように、日本の生産規模は圃場も工場も世界とは比較にならないほど小さい。
(2)南西諸島のサトウキビ産業において労賃、単位収量が示すこと
日本のサトウキビ産業のもう一つの特徴、これは大切なこと、良いことであるが、労賃単価が高いことである。日本は生活水準が高く、基本的には海外のサトウキビ生産国と比べ労賃単価が高い。サトウキビや砂糖のコストとしてのそれも必然的に高くなる。購買力を増し、生活を豊かにするはずの賃金の高さは、産業の競争力という面からは辛い側面として立ち現れることが多い。コスト低減のために人件費総額を減らすことも論理的には可能である。しかし、人件費総額が少ないことは、多数の人がその産業に関わることができないこと、すなわち、産業の人口涵養力が低いことを意味し、地域の基幹産業としては致命的な欠陥を内部に宿すことに他ならない。
生産規模が大きいことがコスト低減の大きな要因であることを先に述べた。労賃単価が低いこともまた同様な意味を持つが、二つとも日本のサトウキビ産業にはない。ならば、規模の拡大や人件費割合の縮小を何処に求めたら良いのだろうか。圃場の面的拡大が不可能だとしたら、空間的・時間的(単位収量) 拡大はどうであろうか。単位収量が高いこと、すなわち土地利用の高度化が一つの道である。同一重量の作物からできる限り多くの価値を取り出すこと、すなわち作物の高度利用も重要な道である。単位収量の世界平均は株出しを含め10アール当たり7トン程度である。株出しは大規模栽培が特徴のブラジル、オーストラリアなどでも5回程度は継続される。日本の場合、株出しの回数は0〜2回のところが多く、収量はおおむね10アール当たり6トンである。生産規模が小さく株出し回数が少ない割には低すぎる収量である。残された道は同じ重量のサトウキビからできる限り大きな価値を生み出すことであるが、現在は大部分の工場が砂糖だけを商品としている。世界の主要国では、砂糖、エタノール、電力が常識的な商品構成である。日本における原料当たり価値創出は世界的には低水準であると言わざるを得ない。
地域の基幹的経済活動としての日本のサトウキビ産業が少しでも自立性を高めるには、面的規模の小ささ、さらには労賃水準の高さを補うに足る単位収量と商品売り上げ量の向上が必要であるが、技術的にはそれは何を意味するのだろうか。地域の農業という立場で考えてみたい。地域の特徴を知ることからそれが始まると思う。
2.島は小さな地球
−半開放系としての島―
日本のサトウキビ産業の主な活動地域は種子島以南に広がる南西諸島の島々である。
都会の日常生活からは遠い亜熱帯の島、珊瑚礁に囲まれた海、近在の海からの魚介の数々、都会とは異なる時間の流れ・・・などが人々を惹きつけてやまない、観光が重要な地域でもある。筆者の住む種子島は温帯最南部にあり、緑濃い山、なだらかな畑、金色に、群青色に深い海の美しさが特徴である。これらをサトウキビ産業の観点で言いなおすと、緑濃い山と畑の島であることは、圃場が海に向かって傾斜していること、すなわち、圃場から土砂が流出し易いこと、また、圃場が狭小であることを意味する。観光が重要産業であることから、景観の維持は必須であるが、珊瑚礁に囲まれた海とは、流入した土砂の逃げ場がないこと、すなわち、圃場からの土砂流出により海浜が汚染され易いことを意味する。
小さな地球としての島で持続的な社会を構築するには、半開放系としての物心の循環(自然環境の維持・涵養を前提に、生活必須物質の自給率を高めた上で外界との物心の交流により富を創出・涵養すること)が必要である。物の交流は生活物資の移出・移入、人(心)の交流は観光である。基幹的経済活動には地域の富創出の最大化に寄与する義務があり、小さな地球の基幹産業であるサトウキビには、上記の活動を支えることが望まれている。複合経営による高価値生産への貢献、観光など関連産業振興への貢献等々については、既に当誌(杉本明;砂糖類情報、2000年7月号 )で論じた。此処ではサトウキビ自身が具えている食料・エネルギーの自給機能、価値創出機能について触れたいと思う。
日本のサトウキビ産業の主な活動地域は種子島以南に広がる南西諸島の島々である。
都会の日常生活からは遠い亜熱帯の島、珊瑚礁に囲まれた海、近在の海からの魚介の数々、都会とは異なる時間の流れ・・・などが人々を惹きつけてやまない、観光が重要な地域でもある。筆者の住む種子島は温帯最南部にあり、緑濃い山、なだらかな畑、金色に、群青色に深い海の美しさが特徴である。これらをサトウキビ産業の観点で言いなおすと、緑濃い山と畑の島であることは、圃場が海に向かって傾斜していること、すなわち、圃場から土砂が流出し易いこと、また、圃場が狭小であることを意味する。観光が重要産業であることから、景観の維持は必須であるが、珊瑚礁に囲まれた海とは、流入した土砂の逃げ場がないこと、すなわち、圃場からの土砂流出により海浜が汚染され易いことを意味する。
小さな地球としての島で持続的な社会を構築するには、半開放系としての物心の循環(自然環境の維持・涵養を前提に、生活必須物質の自給率を高めた上で外界との物心の交流により富を創出・涵養すること)が必要である。物の交流は生活物資の移出・移入、人(心)の交流は観光である。基幹的経済活動には地域の富創出の最大化に寄与する義務があり、小さな地球の基幹産業であるサトウキビには、上記の活動を支えることが望まれている。複合経営による高価値生産への貢献、観光など関連産業振興への貢献等々については、既に当誌(杉本明;砂糖類情報、2000年7月号 )で論じた。此処ではサトウキビ自身が具えている食料・エネルギーの自給機能、価値創出機能について触れたいと思う。
3.基幹産業として目指す方向
(1)今可能な実践
−厳しい生産環境下での安定生産―
南西諸島の全域が台風の常襲地域であり、種子島を除く地域では干ばつ被害が頻発する。
夏に雨が少なく圃場の保水力が低いことが干ばつ被害発生の主因である。その被害最小化は生産技術の重要課題であるが、その即効薬は、台風・干ばつが頻発する時期に抵抗力の高い時期が当たるように作物の生育時期をずらすことである。具体的な方法の一つが夏植え型1年栽培(夏に植えて夏〜秋に収穫し、収穫後の株出しを繰り返す方法)である(杉本明;砂糖類情報、2009年2月号 )。夏植え型1年栽培には、収穫前の台風による糖度の低下、純糖率低下という弱点があったが、現在では「逆転プロセス」(小原聡;砂糖類・でん粉情報、2013年6月号)という救世主的技術が開発され、実現の障壁は以前より遥かに低くなった。
「逆転プロセス」を伴う場合、新しい技術とセットにした形で高い砂糖収率を得れば良いのであり、サトウキビ自体に現在並の高糖性を求める必要はなく、高糖よりは、多収、株出しの充実、台風・干ばつへの抵抗力向上を優先することができる。それで可能になるのがもう一つの方法、既存の高糖性品種に代わり、多収で株出し能力が高く、台風・干ばつに抵抗力の高いサトウキビ品種を利用することである。
現在の砂糖生産は、既存の製糖技術による砂糖抽出効率の最大化を前提に、高糖性サトウキビの生産を重視している。新しい方法では、夏植え型1年栽培も多収性サトウキビの利用も、高糖よりは安定多収を重視して原料を生産し、砂糖生産の最大効率化を新たな製糖技術・システムによって実現しようとしている。限りある圃場から最大限の砂糖を生産するための方法であることに違いはない。ところで、これらは将来の技術であろうか。そうではない。既にこの様なサトウキビが開発されているし、生産支援のための制度にも基本的には矛盾するものではない。
(2)目指すべき実践として
−周年収穫多段階利用―
茎や葉鞘の表面についているワックスが高価なことが知られる(宮城貞夫;砂糖類月報、1994年5・6月号 高村善雄;砂糖類情報、2012年3月号)ように、サトウキビには、砂糖以外にも多くの高価値物質が含まれている。サトウキビからの消臭剤などの製造という大手製糖企業の活動例もある(中島寿典;砂糖類情報、2007年8月号)。ところで、周年収穫多段階利用とはなんだろうか。多段階利用はカスケード(滝)利用とも言われる。要するに、一年中原料を収穫し、サトウキビから、水が滝の上から下に流れるように、サトウキビの成分を価値の高いものから低いものに至るまで直列的に抽出して使い尽くすこと、すなわち、砂糖を含む高価値物質の優先的な商品化によって単位重量のサトウキビから最大の価値を創出しようとするものである。現在の、冬春季に限られた収穫期間、砂糖のみの製造とは大きく異なる、夢のような技術である。しかし、夢のようで夢ではないのがこの技術・システムである。
周年収穫多段階利用を技術的に解剖すると二つの要素に分かれる。一つは、収穫期間の大幅拡張、もう一つは、砂糖を含む高価値物質の効率的な抽出と商品化である。収穫期間の拡張については、植物体の砂糖含有率13.1パーセントを基準に考えた場合、石垣島では9月でも基準に達する系統があることが知られている(杉本明;退職記念講演録、第37回サトウキビ試験成績発表会、2010年)。収穫の終わりを5月としたとき、既存の製糖技術でも9カ月程度の収穫期間が展望される事態になったことを示している。勿論、台風による糖度低下をはじめ、多くの問題がある。しかし、低糖度サトウキビの利用には、「逆転プロセス」という味方がいる。そろそろ「周年」に近い収穫体系を視野に入れた技術開発に取り組む必要がないであろうか。圃場の配置、収穫順序等々、粘り強い検討・調整を要することが多い。そもそも、登熟時期の異なる複数品種の開発が前提である。品種開発は時間のかかる実践である。高価値物質の抽出と商品化については、高村によるほか、三井製糖の商品開発としても試みられている。大規模な抽出は実現していないが、可能性は高いと推察される。どちらもまさに、“今”始めるべき技術開発の実践であろう。
−厳しい生産環境下での安定生産―
南西諸島の全域が台風の常襲地域であり、種子島を除く地域では干ばつ被害が頻発する。
夏に雨が少なく圃場の保水力が低いことが干ばつ被害発生の主因である。その被害最小化は生産技術の重要課題であるが、その即効薬は、台風・干ばつが頻発する時期に抵抗力の高い時期が当たるように作物の生育時期をずらすことである。具体的な方法の一つが夏植え型1年栽培(夏に植えて夏〜秋に収穫し、収穫後の株出しを繰り返す方法)である(杉本明;砂糖類情報、2009年2月号 )。夏植え型1年栽培には、収穫前の台風による糖度の低下、純糖率低下という弱点があったが、現在では「逆転プロセス」(小原聡;砂糖類・でん粉情報、2013年6月号)という救世主的技術が開発され、実現の障壁は以前より遥かに低くなった。
「逆転プロセス」を伴う場合、新しい技術とセットにした形で高い砂糖収率を得れば良いのであり、サトウキビ自体に現在並の高糖性を求める必要はなく、高糖よりは、多収、株出しの充実、台風・干ばつへの抵抗力向上を優先することができる。それで可能になるのがもう一つの方法、既存の高糖性品種に代わり、多収で株出し能力が高く、台風・干ばつに抵抗力の高いサトウキビ品種を利用することである。
現在の砂糖生産は、既存の製糖技術による砂糖抽出効率の最大化を前提に、高糖性サトウキビの生産を重視している。新しい方法では、夏植え型1年栽培も多収性サトウキビの利用も、高糖よりは安定多収を重視して原料を生産し、砂糖生産の最大効率化を新たな製糖技術・システムによって実現しようとしている。限りある圃場から最大限の砂糖を生産するための方法であることに違いはない。ところで、これらは将来の技術であろうか。そうではない。既にこの様なサトウキビが開発されているし、生産支援のための制度にも基本的には矛盾するものではない。
(2)目指すべき実践として
−周年収穫多段階利用―
茎や葉鞘の表面についているワックスが高価なことが知られる(宮城貞夫;砂糖類月報、1994年5・6月号 高村善雄;砂糖類情報、2012年3月号)ように、サトウキビには、砂糖以外にも多くの高価値物質が含まれている。サトウキビからの消臭剤などの製造という大手製糖企業の活動例もある(中島寿典;砂糖類情報、2007年8月号)。ところで、周年収穫多段階利用とはなんだろうか。多段階利用はカスケード(滝)利用とも言われる。要するに、一年中原料を収穫し、サトウキビから、水が滝の上から下に流れるように、サトウキビの成分を価値の高いものから低いものに至るまで直列的に抽出して使い尽くすこと、すなわち、砂糖を含む高価値物質の優先的な商品化によって単位重量のサトウキビから最大の価値を創出しようとするものである。現在の、冬春季に限られた収穫期間、砂糖のみの製造とは大きく異なる、夢のような技術である。しかし、夢のようで夢ではないのがこの技術・システムである。
周年収穫多段階利用を技術的に解剖すると二つの要素に分かれる。一つは、収穫期間の大幅拡張、もう一つは、砂糖を含む高価値物質の効率的な抽出と商品化である。収穫期間の拡張については、植物体の砂糖含有率13.1パーセントを基準に考えた場合、石垣島では9月でも基準に達する系統があることが知られている(杉本明;退職記念講演録、第37回サトウキビ試験成績発表会、2010年)。収穫の終わりを5月としたとき、既存の製糖技術でも9カ月程度の収穫期間が展望される事態になったことを示している。勿論、台風による糖度低下をはじめ、多くの問題がある。しかし、低糖度サトウキビの利用には、「逆転プロセス」という味方がいる。そろそろ「周年」に近い収穫体系を視野に入れた技術開発に取り組む必要がないであろうか。圃場の配置、収穫順序等々、粘り強い検討・調整を要することが多い。そもそも、登熟時期の異なる複数品種の開発が前提である。品種開発は時間のかかる実践である。高価値物質の抽出と商品化については、高村によるほか、三井製糖の商品開発としても試みられている。大規模な抽出は実現していないが、可能性は高いと推察される。どちらもまさに、“今”始めるべき技術開発の実践であろう。
4.すぐ其処の実践
−砂糖・エタノール・電力・有機質資源複合生産―
周年収穫多段階利用への一里塚として、現実の産業的実践として今何ができるだろうか。それが、収穫期間の長期化、多回株出し多糖性サトウキビの開発と利用を伴う、「砂糖・エタノール・電力・有機質資源複合生産」(南西諸島ビジョン)である。
日本のサトウキビ主産地は南の島々である。電力やガソリン、エネルギーの主産地からは遠く隔たり、エネルギーの生産や輸送にエネルギー(コスト)付加を要する地域である。世界的には、サトウキビから砂糖・エタノール・電力を生産することは常識の感があるが、日本の場合、小規模故の採算割れは想像に難くない。しかし、現在は家庭で生産した電気を電力会社が買う時代、畑に太陽光発電のパネルが並ぶ時代である。製糖工場は発電機を備え、電力を自給している。その拡大としての地域への電力供給、その実用的技術・システムの構築は不可能であろうか。
経済的生産の隘路、その第1は電力の生産量が小さく生産性が低いこと、第2は製糖工場の稼動期間が短く年間を通した地域への電力供給には安定性が欠けること、と推察される。これは克服不可能であろうか。稼動期間については、製糖工場操業期間の9カ月程度までの拡張が射程に入っている。電力生産量増加は、余剰バガスの飛躍的な増加、すなわちサトウキビ繊維分の増加によって達成される。これまで繊維分が高いサトウキビは、バガスの有効な利用がないことから、蔗汁の抽出を阻害するものにすぎないとされて敬遠されてきた。繊維分の高さが(繊維に電力換算などによる価値を与えることで)許容されれば、サトウキビの収量増が可能になることは容易に想像される。離島におけるエネルギー生産の社会的意義、それへの公的支援を期待することも許されて良いであろう。エタノール生産については逆転プロセスを中心とするアサヒグループHDの取り組みが一つの解である。持続性の獲得には、非利用部分の飼料化、畜産との連携による地力の維持・改良(地力改良型作物生産)が重要である。製糖工場を地域の食料・エネルギーの持続的な生産・供給基地として位置づけること、その姿は未来のものではなく、優れて現在のものであるといえよう。
周年収穫多段階利用への一里塚として、現実の産業的実践として今何ができるだろうか。それが、収穫期間の長期化、多回株出し多糖性サトウキビの開発と利用を伴う、「砂糖・エタノール・電力・有機質資源複合生産」(南西諸島ビジョン)である。
日本のサトウキビ主産地は南の島々である。電力やガソリン、エネルギーの主産地からは遠く隔たり、エネルギーの生産や輸送にエネルギー(コスト)付加を要する地域である。世界的には、サトウキビから砂糖・エタノール・電力を生産することは常識の感があるが、日本の場合、小規模故の採算割れは想像に難くない。しかし、現在は家庭で生産した電気を電力会社が買う時代、畑に太陽光発電のパネルが並ぶ時代である。製糖工場は発電機を備え、電力を自給している。その拡大としての地域への電力供給、その実用的技術・システムの構築は不可能であろうか。
経済的生産の隘路、その第1は電力の生産量が小さく生産性が低いこと、第2は製糖工場の稼動期間が短く年間を通した地域への電力供給には安定性が欠けること、と推察される。これは克服不可能であろうか。稼動期間については、製糖工場操業期間の9カ月程度までの拡張が射程に入っている。電力生産量増加は、余剰バガスの飛躍的な増加、すなわちサトウキビ繊維分の増加によって達成される。これまで繊維分が高いサトウキビは、バガスの有効な利用がないことから、蔗汁の抽出を阻害するものにすぎないとされて敬遠されてきた。繊維分の高さが(繊維に電力換算などによる価値を与えることで)許容されれば、サトウキビの収量増が可能になることは容易に想像される。離島におけるエネルギー生産の社会的意義、それへの公的支援を期待することも許されて良いであろう。エタノール生産については逆転プロセスを中心とするアサヒグループHDの取り組みが一つの解である。持続性の獲得には、非利用部分の飼料化、畜産との連携による地力の維持・改良(地力改良型作物生産)が重要である。製糖工場を地域の食料・エネルギーの持続的な生産・供給基地として位置づけること、その姿は未来のものではなく、優れて現在のものであるといえよう。
おわりに
2年連続の不作に関係者全員が心を痛め、頭を悩ませる中、敢えてその直接的な技術対策には触れず、今後の進むべき方向に筆を向けた。それは、日本のサトウキビ産業は、豊作時にあってさえも衰退の道にあり、その本質的克服こそが技術開発の第一の任務であることを、このような苦しい時にも忘れないでおこうとする筆者の意思である。同時に、本稿で示す進む道とは、そもそも、自然科学的にも社会科学的にも厳しい、2重の厳しさにある日本のサトウキビ産業の安定多収の実現、産業持続性の向上を目指すものであることから、この道を進むことこそが、2年連続の不作を克服する最も効果的な道、しかも優れて現在の実践であると思うからである。諸氏のお叱りを受けたいと思う。
(プロフィール)
杉本 明(すぎもと あきら)
昭和50年 東京教育大学大学院農学研究科修士課程修了。同年、沖縄県八重山支庁入庁。九州農業試験場サトウキビ育種研究室長、九州沖縄農業研究センター作物機能開発部長などを歴任。平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞などを受賞。現在はサトウキビコンサルタントとして活動。
(プロフィール)
杉本 明(すぎもと あきら)
昭和50年 東京教育大学大学院農学研究科修士課程修了。同年、沖縄県八重山支庁入庁。九州農業試験場サトウキビ育種研究室長、九州沖縄農業研究センター作物機能開発部長などを歴任。平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞などを受賞。現在はサトウキビコンサルタントとして活動。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678