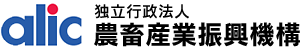ホーム > 砂糖 > お砂糖豆知識 > 江戸時代の砂糖食文化
最終更新日:2011年4月8日
江戸時代の砂糖食文化 〜砂糖の流通と砂糖菓子〜
2011年4月
北九州市立大学文学部 教授 八百 啓介
1.大坂から江戸への砂糖の流通
江戸時代に長崎に来航する唐船・オランダ船によって輸入された砂糖は、生糸などの輸入品を大坂に回送する糸荷廻船で大坂の唐薬種問屋に運ばれた。当時、砂糖を積んだ船は「堺船」と呼ばれたという。元禄10年(1697)の長崎会所設立に際して、幕府御用の御菓子屋であった大久保主水と虎屋織部に対して、砂糖を元値段で買い取ることが許された。その額は寛延2年(1749)の貿易半減令の翌年には金660両(現在の価値でおよそ数千万円)分となった。またその量は2万7650斤(16.59トン)であり、同年の輸入量全体の約1%であった。それ以外の長崎会所で貨物本商人に落札された輸入砂糖は、大坂の唐薬種問屋から砂糖荒物仲買仲間の手を経て、江戸をはじめ全国に運ばれた。
大坂堺筋の砂糖荒物仲買仲間は一番組(戎講)・二番組(大黒講)・三番組(三社講)の3グループに分かれており、それぞれ仲間から選出された世話役によって支配されていた。また天明元年(1781)には輸入品の流通統制と安定供給とを目的として株仲間となったが、その数は江戸時代の終わりには200軒におよんだ。
18世紀初めの正徳3年(1713)から薩摩産の黒砂糖が大坂の薩州問屋を経て販売されるようになったが、さらに18世紀末の寛政6年(1794)から紀州・讃岐などの国内産白砂糖が大坂にもたらされると、各藩の蔵屋敷のほか唐薬種問屋が引き受けた。天保5年(1834)には国産白砂糖を専門に扱う和砂糖問屋が株仲間となったほか、砂糖仲買仲間三講からも、それぞれ長久講・栄寿講・栄久講の和砂糖専門の講が分出した。
なお今日、大阪の住吉神社には、天保11年(1840)に和砂糖問屋が奉納した石灯籠、弘化4年(1847)と嘉永元年(1848)に一番組仲買仲間が奉納した石灯籠が残っている。
当時最大の消費地であった江戸への砂糖の輸送は、江戸との取引を独占していた二十四組問屋によって行われた。一方、江戸市中における砂糖の流通は、大坂との取引を独占していた十組問屋に属する薬種問屋50軒の手によって行われていた。薬種問屋の仲間の内訳は、薬種25軒・砂糖25軒であったが、19世紀初頭の享和年間に大伝馬町の薬種問屋であった大坂屋勘兵衛・堺屋九左衛門が砂糖専業となり、薬種問屋50軒のうち30数軒が砂糖問屋になったという。
大坂から江戸への商品の輸送は、当初、菱垣廻船によって行われていたが、西宮の酒を江戸に送るための樽廻船が始まると、砂糖輸送の権利を巡ってしばしば争いが起きた。
天明6年(1786)に大坂・江戸の薬種問屋が砂糖の輸送をもっぱら樽廻船とすると、江戸における砂糖問屋は「住吉講」を称するようになった。住吉社は大坂と江戸佃島にあって、当時、大坂・江戸間の海上交通の守護神として信仰を集めていた。また鎌倉の鶴岡八幡宮には文久2年(1862)に江戸・大坂の砂糖屋が奉納した石灯籠2基が残っているが、さきほどの住吉神社の石灯籠と合わせて海上航海の安全を祈願したものである。
大坂堺筋の砂糖荒物仲買仲間は一番組(戎講)・二番組(大黒講)・三番組(三社講)の3グループに分かれており、それぞれ仲間から選出された世話役によって支配されていた。また天明元年(1781)には輸入品の流通統制と安定供給とを目的として株仲間となったが、その数は江戸時代の終わりには200軒におよんだ。
18世紀初めの正徳3年(1713)から薩摩産の黒砂糖が大坂の薩州問屋を経て販売されるようになったが、さらに18世紀末の寛政6年(1794)から紀州・讃岐などの国内産白砂糖が大坂にもたらされると、各藩の蔵屋敷のほか唐薬種問屋が引き受けた。天保5年(1834)には国産白砂糖を専門に扱う和砂糖問屋が株仲間となったほか、砂糖仲買仲間三講からも、それぞれ長久講・栄寿講・栄久講の和砂糖専門の講が分出した。
なお今日、大阪の住吉神社には、天保11年(1840)に和砂糖問屋が奉納した石灯籠、弘化4年(1847)と嘉永元年(1848)に一番組仲買仲間が奉納した石灯籠が残っている。
当時最大の消費地であった江戸への砂糖の輸送は、江戸との取引を独占していた二十四組問屋によって行われた。一方、江戸市中における砂糖の流通は、大坂との取引を独占していた十組問屋に属する薬種問屋50軒の手によって行われていた。薬種問屋の仲間の内訳は、薬種25軒・砂糖25軒であったが、19世紀初頭の享和年間に大伝馬町の薬種問屋であった大坂屋勘兵衛・堺屋九左衛門が砂糖専業となり、薬種問屋50軒のうち30数軒が砂糖問屋になったという。
大坂から江戸への商品の輸送は、当初、菱垣廻船によって行われていたが、西宮の酒を江戸に送るための樽廻船が始まると、砂糖輸送の権利を巡ってしばしば争いが起きた。
天明6年(1786)に大坂・江戸の薬種問屋が砂糖の輸送をもっぱら樽廻船とすると、江戸における砂糖問屋は「住吉講」を称するようになった。住吉社は大坂と江戸佃島にあって、当時、大坂・江戸間の海上交通の守護神として信仰を集めていた。また鎌倉の鶴岡八幡宮には文久2年(1862)に江戸・大坂の砂糖屋が奉納した石灯籠2基が残っているが、さきほどの住吉神社の石灯籠と合わせて海上航海の安全を祈願したものである。
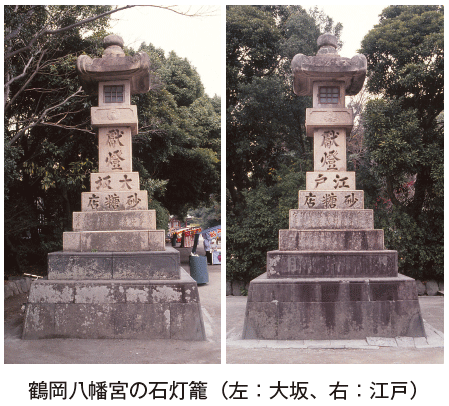
2.江戸時代の砂糖と和菓子
今日、和菓子と砂糖といえば、小豆餡の材料として広く用いられているが、江戸時代の初めまでは餡といえばもっぱら味噌味や塩味であった。
鎌倉時代に禅僧の間食として伝えられた饅頭は、前回述べたように、すでに室町時代には砂糖を材料とするようになったが、嘉永6年(1853)の『近世風俗志(守貞漫稿)』の「饅頭」の項によれば 「昔は菜饅頭・砂糖饅頭の二制あり。何時よりか菜饅頭は廃れて、今は砂糖饅頭のみなり。今の饅頭、表は小麦粉を皮とし、中に小豆餡を納る。小豆は皮を去り砂糖を加ふ。砂糖に白黒の二品あり。白を白餡と云ひ、黒をくろあんと云ふ。(中略)昔は諸国ともに菜饅頭廃し、その後は塩饅頭と云ひて小豆餡に塩を加へたり。(中略)近世は鄙といへども皆専ら砂糖万十なり。文化以来、やうやうかくのごとくなり。」 とあり、江戸時代の初めには菜饅頭と砂糖饅頭の二つの系統であったものが、塩饅頭を経て19世紀初めの文化年間に入るともっぱら砂糖饅頭が普及していったことが分かる。
日本最初の菓子製法書である享保3年(1718)の『古今名物御前菓子秘伝抄』によれば、当時すでに羊羹は小豆と白砂糖を材料とする砂糖羊羹であったが、柏餅は煮てすり潰した小豆に塩を加えた塩餡の餅であった。一説には17世紀の中頃の正保年間に創製された当初は味噌餡であったという。前述の『近世風俗志(守貞漫稿)』によれば、幕末の柏餅には砂糖入り小豆餡が用いられているが、虎屋文庫の中山圭子氏によれば、柏の葉の裏表で小豆餡と味噌餡とを区別していたという。
文化・文政期の戯作者であった滝沢馬琴の日記によれば、文政11年(1829)の端午の節句には「つるや」に柏餅を注文しているが、翌年からは黒砂糖を購入して自家製の柏餅を350〜360個も作るようになったことがわかる。天保4年(1833)の日記によれば、前年黒砂糖を購入した小松屋の砂糖の値段が200文近くに値上がりしたため、下女を近所の紀伊国屋に遣わして1斤当り172文で2斤買わせている。
今日、饅頭・羊羹・柏餅とともに小豆餡の欠かせない大福餅は、「鶉焼(うずらやき)(鶉餅(うずらもち))」あるいは「腹太餅(はらふともち)」という大ぶりな餡入りの餅がもととなって江戸で考案されたといわれている。その創製は明和8〜9年(1771〜72)とも寛政年間ともいわれているが、もともと鶉焼も腹太餅も小豆の塩餡であったという。
鎌倉時代に禅僧の間食として伝えられた饅頭は、前回述べたように、すでに室町時代には砂糖を材料とするようになったが、嘉永6年(1853)の『近世風俗志(守貞漫稿)』の「饅頭」の項によれば 「昔は菜饅頭・砂糖饅頭の二制あり。何時よりか菜饅頭は廃れて、今は砂糖饅頭のみなり。今の饅頭、表は小麦粉を皮とし、中に小豆餡を納る。小豆は皮を去り砂糖を加ふ。砂糖に白黒の二品あり。白を白餡と云ひ、黒をくろあんと云ふ。(中略)昔は諸国ともに菜饅頭廃し、その後は塩饅頭と云ひて小豆餡に塩を加へたり。(中略)近世は鄙といへども皆専ら砂糖万十なり。文化以来、やうやうかくのごとくなり。」 とあり、江戸時代の初めには菜饅頭と砂糖饅頭の二つの系統であったものが、塩饅頭を経て19世紀初めの文化年間に入るともっぱら砂糖饅頭が普及していったことが分かる。
日本最初の菓子製法書である享保3年(1718)の『古今名物御前菓子秘伝抄』によれば、当時すでに羊羹は小豆と白砂糖を材料とする砂糖羊羹であったが、柏餅は煮てすり潰した小豆に塩を加えた塩餡の餅であった。一説には17世紀の中頃の正保年間に創製された当初は味噌餡であったという。前述の『近世風俗志(守貞漫稿)』によれば、幕末の柏餅には砂糖入り小豆餡が用いられているが、虎屋文庫の中山圭子氏によれば、柏の葉の裏表で小豆餡と味噌餡とを区別していたという。
文化・文政期の戯作者であった滝沢馬琴の日記によれば、文政11年(1829)の端午の節句には「つるや」に柏餅を注文しているが、翌年からは黒砂糖を購入して自家製の柏餅を350〜360個も作るようになったことがわかる。天保4年(1833)の日記によれば、前年黒砂糖を購入した小松屋の砂糖の値段が200文近くに値上がりしたため、下女を近所の紀伊国屋に遣わして1斤当り172文で2斤買わせている。
今日、饅頭・羊羹・柏餅とともに小豆餡の欠かせない大福餅は、「鶉焼(うずらやき)(鶉餅(うずらもち))」あるいは「腹太餅(はらふともち)」という大ぶりな餡入りの餅がもととなって江戸で考案されたといわれている。その創製は明和8〜9年(1771〜72)とも寛政年間ともいわれているが、もともと鶉焼も腹太餅も小豆の塩餡であったという。
3.江戸時代の砂糖飴と砂糖漬
砂糖がもたらされる以前の庶民の甘味料は、ヨーロッパでは蜂蜜であり日本では飴であった。飴はもち米などのデンプンを麦芽(麦もやし)で糖化して作られる我が国古来の甘味料であり、『日本書紀』において初代の天皇とされる神武天皇の即位前紀に「飴(たがね)」が記されているほか『延喜式』には平安時代の都に「糖(あめ)」の店があったとされる。
江戸時代になって長崎に来航する唐船・オランダ船により砂糖が大量に輸入されるようになると、金平糖などの南蛮菓子のほか従来の飴に加えて、新たに砂糖を用いた飴が作られるようになる。
すなわち日本最初の菓子製法書である享保3年(1718)の『古今名物御前菓子秘伝抄』には、砂糖1斤、うどん粉(小麦粉)10匁、蕨(わらび)粉5匁、葛粉5匁、水飛の粉(白玉粉)5匁に水1升を入れ、炭火で練り詰める「唐飴」の製法が紹介されている。ちなみに同書には「唐人飴」の製法も記載されているが、「唐飴」が砂糖飴であるのに対して、「唐人飴」は餅米に麦もやしを加えた従来の麦芽飴である。
さらに文化2年(1805)の『餅菓子即席手製集』には、白砂糖3斤を水2升で煎じ詰め、餅米3合、水飴を飯椀1杯、酢を杯1杯と加えた「三貫飴」や、餅米1升を水ですり合わせ、白砂糖6斤を入れ煎じ詰めた「南蛮飴」の製法が記載されるなど、江戸時代になると日本古来の飴の製法にも砂糖が用いられるようになった。
江戸時代の砂糖を使った菓子はカステラ・饅頭・羊羹などの和菓子だけではない。文久2年(1862)の『古今新製名菓秘録』には天門冬(てんもんどう)・仏手柑(ぶしゅかん)・キンカンの柑橘類のほか、ショウガ・レンコン・タケノコ・シイタケ・ナス・キュウリ・スイカ・冬瓜(とうがん)・ゴボウ・ニンジンの野菜類や豆腐にいたる様々な種類の砂糖漬が紹介されている。このことから江戸時代には砂糖が菓子の材料のみならず、保存料としても用いられていたことがわかる。
江戸時代における砂糖漬は、ポルトガル菓子のコンフェイト(Confeitos)すなわち砂糖漬がもとになったと思われる。今日、コンフェイトは金平糖の語源として知られる。金平糖ももともとは砂糖だけではなくケシ粒を砂糖でくるんだ砂糖漬の一種であり、コンフェイトとはジャムをはじめとする果物などの保存食全体をさすものであった。さらに我が国においては、イエズス会宣教師の布教活動や鎖国時代のオランダ商館での饗応など日欧間の交流に欠かせない食物であった。鎖国時代や毎年江戸に参府したオランダ商館長は、旅先での接待のために砂糖漬けを江戸まで持参している。
さらに興味深いことに天明5年(1785)の『柚珍秘密箱(ゆうちんひみつばこ)』の「柚砂糖漬仕方」によれば、ユズを黒砂糖の蜜に10日間とひと晩の2度漬けた後の仕上げのみに白砂糖の蜜が用いられている。これに対して、長崎に隣接した佐賀の丸ぼうろの老舗である「鶴屋」堤家に伝わる宝暦6年(1756)頃の『菓子仕方控覚』の「砂糖漬仕方」によれば、蜜には白砂糖のみが用いられており、江戸よりも白砂糖の入手が容易であったことがうかがえる。
江戸時代になって長崎に来航する唐船・オランダ船により砂糖が大量に輸入されるようになると、金平糖などの南蛮菓子のほか従来の飴に加えて、新たに砂糖を用いた飴が作られるようになる。
すなわち日本最初の菓子製法書である享保3年(1718)の『古今名物御前菓子秘伝抄』には、砂糖1斤、うどん粉(小麦粉)10匁、蕨(わらび)粉5匁、葛粉5匁、水飛の粉(白玉粉)5匁に水1升を入れ、炭火で練り詰める「唐飴」の製法が紹介されている。ちなみに同書には「唐人飴」の製法も記載されているが、「唐飴」が砂糖飴であるのに対して、「唐人飴」は餅米に麦もやしを加えた従来の麦芽飴である。
さらに文化2年(1805)の『餅菓子即席手製集』には、白砂糖3斤を水2升で煎じ詰め、餅米3合、水飴を飯椀1杯、酢を杯1杯と加えた「三貫飴」や、餅米1升を水ですり合わせ、白砂糖6斤を入れ煎じ詰めた「南蛮飴」の製法が記載されるなど、江戸時代になると日本古来の飴の製法にも砂糖が用いられるようになった。
江戸時代の砂糖を使った菓子はカステラ・饅頭・羊羹などの和菓子だけではない。文久2年(1862)の『古今新製名菓秘録』には天門冬(てんもんどう)・仏手柑(ぶしゅかん)・キンカンの柑橘類のほか、ショウガ・レンコン・タケノコ・シイタケ・ナス・キュウリ・スイカ・冬瓜(とうがん)・ゴボウ・ニンジンの野菜類や豆腐にいたる様々な種類の砂糖漬が紹介されている。このことから江戸時代には砂糖が菓子の材料のみならず、保存料としても用いられていたことがわかる。
江戸時代における砂糖漬は、ポルトガル菓子のコンフェイト(Confeitos)すなわち砂糖漬がもとになったと思われる。今日、コンフェイトは金平糖の語源として知られる。金平糖ももともとは砂糖だけではなくケシ粒を砂糖でくるんだ砂糖漬の一種であり、コンフェイトとはジャムをはじめとする果物などの保存食全体をさすものであった。さらに我が国においては、イエズス会宣教師の布教活動や鎖国時代のオランダ商館での饗応など日欧間の交流に欠かせない食物であった。鎖国時代や毎年江戸に参府したオランダ商館長は、旅先での接待のために砂糖漬けを江戸まで持参している。
さらに興味深いことに天明5年(1785)の『柚珍秘密箱(ゆうちんひみつばこ)』の「柚砂糖漬仕方」によれば、ユズを黒砂糖の蜜に10日間とひと晩の2度漬けた後の仕上げのみに白砂糖の蜜が用いられている。これに対して、長崎に隣接した佐賀の丸ぼうろの老舗である「鶴屋」堤家に伝わる宝暦6年(1756)頃の『菓子仕方控覚』の「砂糖漬仕方」によれば、蜜には白砂糖のみが用いられており、江戸よりも白砂糖の入手が容易であったことがうかがえる。
《参考文献》
湯浅三精編『東京砂糖貿易商同業組合沿革史』東京砂糖貿易商同業組合1938年
樋口弘『日本糖業史』内外経済社1956年
暉峻康隆他校訂『馬琴日記』中央公論社1973年
喜多川守貞著・宇佐美英機校訂『近世風俗志(一)』岩波書店1996年
原田信男校註・解説『料理百珍集』八坂書房1997年
鈴木晋一・松本仲子編訳注『近世菓子製法書集成1』平凡社2003年
中山圭子『事典 和菓子の世界』岩波書店2006年
樋口弘『日本糖業史』内外経済社1956年
暉峻康隆他校訂『馬琴日記』中央公論社1973年
喜多川守貞著・宇佐美英機校訂『近世風俗志(一)』岩波書店1996年
原田信男校註・解説『料理百珍集』八坂書房1997年
鈴木晋一・松本仲子編訳注『近世菓子製法書集成1』平凡社2003年
中山圭子『事典 和菓子の世界』岩波書店2006年
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8713