

ホーム > 砂糖 > インドの砂糖産業の概要 〜砂糖生産と政策〜
最終更新日:2010年4月16日
調査・報告[2010年04月]
調査情報部 調査課
1.さとうきび生産状況
2.砂糖の需給動向
3.砂糖政策
4.エタノール生産の現状
5.砂糖産業をめぐる課題
はじめに
2009年の砂糖国際価格は、インドが2008/09年度において穀物価格の高騰を背景に、さとうきびから穀物への作付転換が行われ、さとうきび作付面積が減少したことやモンスーン期の少雨による生産量の減少から自給国から輸入国に転換し、また、EUの砂糖制度改革による輸出量の大幅な減少などにより大幅に上昇した。
砂糖の需給構造が大きく変化した中で、最大の砂糖消費国であり、ブラジルに次ぐさとうきび生産国であるインドの動向が注目されている。
本稿では、英国の調査会社LMCからの直近の報告、これまでの現地調査などを基に、近年のインドの砂糖産業について取りまとめたので紹介する。
砂糖の需給構造が大きく変化した中で、最大の砂糖消費国であり、ブラジルに次ぐさとうきび生産国であるインドの動向が注目されている。
本稿では、英国の調査会社LMCからの直近の報告、これまでの現地調査などを基に、近年のインドの砂糖産業について取りまとめたので紹介する。
1.さとうきび生産状況
さとうきび生産額は、農業生産額の3%〜5%を占めており、砂糖産業が生み出している直接雇用は100万人、貿易等の関連産業雇用も100万人ともいわれ、インド経済にとって重要な位置を占めている。
また、さとうきびの収穫量は、ブラジルに次ぎ世界で2番目に多く、この5年間では、年間収穫量が2億4000万〜3億5500万トンであった。このうち、遠心分離装置により砂糖を生産する製糖工場に使われるさとうきびの割合は50%〜75%、残りのさとうきびは、グル(gur:solidified cane juice)およびカンサリ(khandsari:semi―white centrifugal sugar)(注)と呼ばれる砂糖を伝統的なオープンパン(open―pan)製法で製造する部門に供給されている。
製糖工場とグル・カンサリ製造業者の間には、製糖工場が、後述するように政府の価格政策(法定最低価格(SMP:Statutory Minimum Price)及び州勧告価格(SAP:State Advised Price)によるさとうきび買付価格、公共流通制度(Public Distribution System)よる販売数量等に基づき経営しなければならないのに対し、グル・カンサリ製造業者は、零細家内工業が多いものの自由な買付・販売、価格設定ができるという大きな違いがある。
注:グルは、遠心分離機を使わず、オープンパン(釜炊き)でさとうきびの搾汁を煮詰め、固形状もしくは板状にした砂糖。カンサリは、搾汁液を清浄化した後、オープンパンで煮詰め、分みつした砂糖。
また、さとうきびの収穫量は、ブラジルに次ぎ世界で2番目に多く、この5年間では、年間収穫量が2億4000万〜3億5500万トンであった。このうち、遠心分離装置により砂糖を生産する製糖工場に使われるさとうきびの割合は50%〜75%、残りのさとうきびは、グル(gur:solidified cane juice)およびカンサリ(khandsari:semi―white centrifugal sugar)(注)と呼ばれる砂糖を伝統的なオープンパン(open―pan)製法で製造する部門に供給されている。
製糖工場とグル・カンサリ製造業者の間には、製糖工場が、後述するように政府の価格政策(法定最低価格(SMP:Statutory Minimum Price)及び州勧告価格(SAP:State Advised Price)によるさとうきび買付価格、公共流通制度(Public Distribution System)よる販売数量等に基づき経営しなければならないのに対し、グル・カンサリ製造業者は、零細家内工業が多いものの自由な買付・販売、価格設定ができるという大きな違いがある。
注:グルは、遠心分離機を使わず、オープンパン(釜炊き)でさとうきびの搾汁を煮詰め、固形状もしくは板状にした砂糖。カンサリは、搾汁液を清浄化した後、オープンパンで煮詰め、分みつした砂糖。
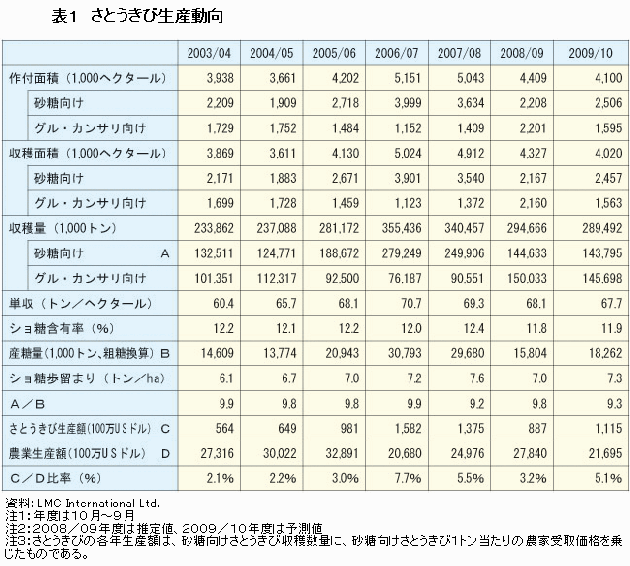
(1) さとうきび生産
さとうきびの作付面積は、価格変動や収益面からの競合作物からの転換等による変動を繰り返しながらも増加傾向をたどり、1960年代初めの約240万haから1990代半ばで約400万haに達し、2006/07年度は515万haまで増加した。その後、国際砂糖価格の下落や国際穀物価格の高騰などを背景にさとうきびから穀物への作付転換が進行したことなどから、2009/10年度は410万haに減少する見込みである。
一方、さとうきびの収穫量は、作付面積の変動に加え、気候条件や天水灌漑の脆弱性等により変動が大きいものの、1960年代初めの1.1億トンから2006/07年度には3.55億トンに増加した。2009/10年度の収穫量は、作付面積の減少、モンスーン期の少雨から2.9億トンにとどまる見込みである。また、1ヘクタール当たりの収量は、1960年代初めのヘクタール当たり45トン程度から近年は同70トン程度に増加しており、作付面積の増減が砂糖生産量に大きく影響するようになっている。
(2) さとうきび生産地域
表2 さとうきびの州別生産動向
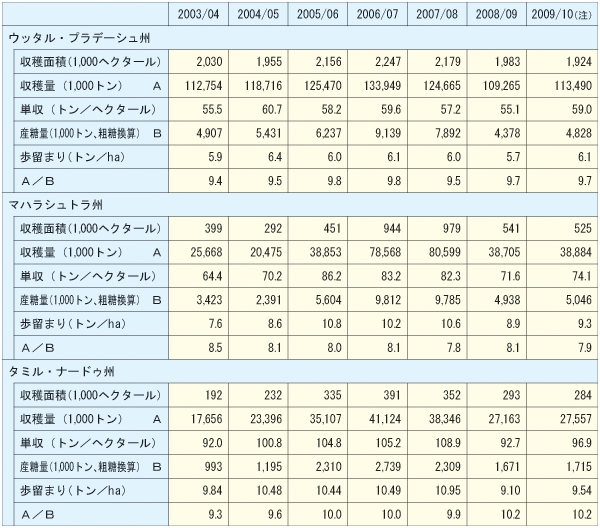
資料:LMC
注:2008/09年度は推定値、2009/10年度は予測値
さとうきびの栽培はインド各地で行われているが、主な生産地域は、ウッタル・プラデーシュ(Uttar Pradesh)州、パンジャブ(Punjab)州、ハリヤナ(Haryana)州、ビハール(Bihar)州などの北部亜熱帯地方、マハーラーシュトラ(Maharashtra)州、グジャラート(Gujarat)州の西部熱帯地方、タミル・ナードゥ(Tamil Nadu)州、カルナータカ(Karnataka)州、ケララ(Kerala)州の南部熱帯地方である。 しかし、その生産は、ウッタル・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、タミル・ナードゥ州に集中しており、これら3州を合わせるとインド全体の収穫量の70%を占めている。
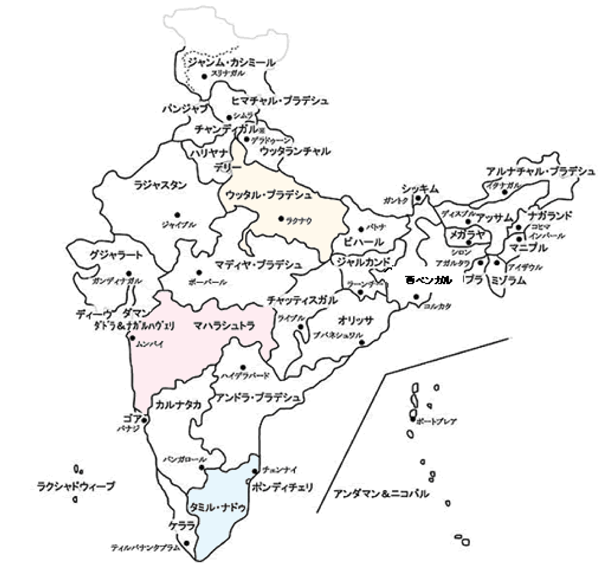
図1 インドの州と主要都市
これを作付面積で見ると、ウッタル・プラデーシュ州が全国の50%、マハーラーシュトラ州が13%程度、タミルナードゥ州が10%程度を占めているが、1ヘクタール当たりの収量では、タミル・ナードゥ州が90〜110トン、マハーラーシュトラ州が70〜90トン、ウッタル・プラデーシュ州が55〜60トンと気象条件やかんがい設備などにより大きく異っている。ウッタル・プラデーシュ州ではヒマラヤ山脈からの地下水の利用により作柄が安定しているものの、亜熱帯性気候のため株出し回数が1〜2回に制約されることや、小規模農家が多いことなどにより単収が他の2州より低く、熱帯性気候に位置するマハーラーシュトラ州やタミルナードゥ州では2〜3回の株出し、マハーラーシュトラ州においてはかんがい設備の整備により高い単収をあげている。砂糖生産量では、マハーラーシュトラ州が最大、次いでウッタル・プラデーシュ州となっている。
なお、ショ糖歩留まり(単位面積当たりのショ糖収量)は、さとうきびの品質向上のための助成制度などがないため、主な砂糖生産国と比べると改善が進んでいない。
2.砂糖の需給動向
(1) 製糖工場の所有形態
インドでは製糖工場の所有形態を、協同組合(Co―op Sector)、民間(Private Sector)、公営(Public Sector)の3つに分けることができる。協同組合工場の場合、組合員である傘下のさとうきび栽培農家には、その工場の各年度の利益を基に支払いが行われる。マハーラーシュトラ州では、特に協同組合部門の影響力が強い。民間工場は、ウッタル・プラデーシュ州、カルナータカ州、タミルナードゥ州など南部の州に多い。公営工場の数が最も多いのはウッタル・プラデーシュ州とビハール州である。このなかには、民間工場であったが、業績不振によって、州政府が経営を引き継いだケースも少なくない。
なお、2006年9月のインド製糖業者協会(ISMA:Indian Sugar Mills Association)の統計によれば、全国568工場のうち、協同組合が315工場(シェア55.5%)、民間が191工場(同33.6%)、公営が62工場(同10.9%)、生産能力1899万トンのうち、協同組合が1068万トン(同56.3%)、民間が710万トン(同37.4%)、公営が120万トン(同6.3%)である。
なお、2006年9月のインド製糖業者協会(ISMA:Indian Sugar Mills Association)の統計によれば、全国568工場のうち、協同組合が315工場(シェア55.5%)、民間が191工場(同33.6%)、公営が62工場(同10.9%)、生産能力1899万トンのうち、協同組合が1068万トン(同56.3%)、民間が710万トン(同37.4%)、公営が120万トン(同6.3%)である。
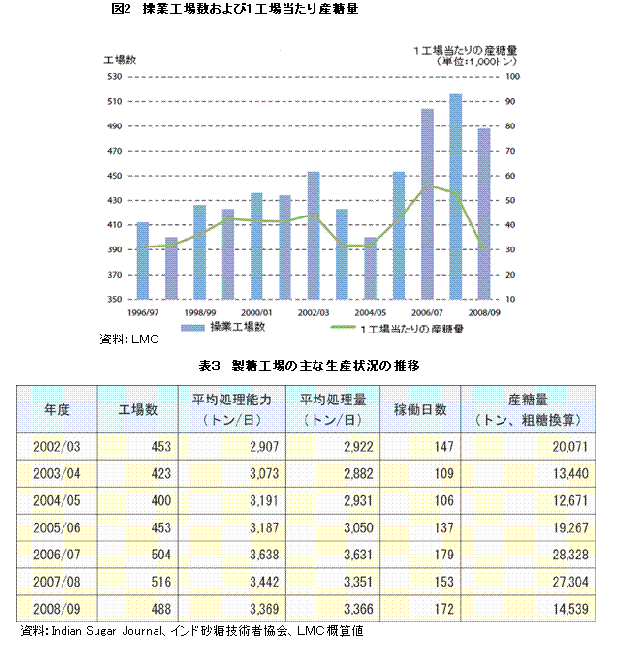
(2) 製糖工場の実績
インドにおける砂糖政策は、1952年にIndustries(Development and Regulation)Act 1951の施行により、砂糖工場許可制度、さとうきび価格制度、徴収砂糖および自由販売砂糖の販売・流通制度が開始され、その後、自由化が進められる中で、砂糖工場許可制度が1998年9月に廃止された。砂糖工場許可制度下では、新規工場の許可を南部熱帯地域に優先的に与えることにより南部地域の砂糖産業が発展し、また、工場新増設許可の条件として、当初は1日当たりのさとうきび処理能力が2,500トン以内とされていたが、その後の改正で同2,500トン以上となったことにより工場の規模拡大が進んだ。
その後、こうした許認可制度がなくなり、2,500トンをはるかに超える処理能力を持つ工場の新増設により平均処理能力も拡大してきた。現在では、大規模工場と比較的規模の小さな工場が混在している。
最近の平均処理能力、平均処理量を見ると、2006/07年度をピークに減少しており、また、工場数は、さとうきびが2年連続の不作となり操業工場数が減った2003/04年度、2004/05年度を除き、2007/08年度まで概ね増加傾向で推移し516に達したが、2008/09年度になると、さとうきび不足の影響で再び多くの工場が操業を停止し、488に減少している。
また、輸入粗糖を原料とする精製糖については、これまでごくわずかしか生産されてこなかった状況がここ数年で変わりつつあり、東海岸に精糖工場が2つ新設されたほか、西部に新たな精糖工場も建設中である。
(1)Shree Renuka社
2008年10月、ハーディア(Haldia、西ベンガル州)に、1日当たり約2,000トンの処理能力を持つ精糖工場を開業
(2)Silkroad Sugar Pvt社
Cargill社、EID Parry社は、港に本拠を置く精糖工場として、合併企業Silkroad Sugar Pvt社をカーキナーダ(Kakinada、アンドラプラデシュ州)に設立した。処理能力は現在、年間60万トンであるが、将来的に100万トンにまで増強する。製造した精製糖の再輸出先は、南アジアと東南アジアに絞るとしている。
(3)Shree Renuka社
Cargill社とEID Parry社が、ムンドラ(Mundra、グラジャート州)に2つ目の精糖工場を建設している。60万トンの生産能力を持つ見通しで、2011/12年度に操業を開始する予定である。
その後、こうした許認可制度がなくなり、2,500トンをはるかに超える処理能力を持つ工場の新増設により平均処理能力も拡大してきた。現在では、大規模工場と比較的規模の小さな工場が混在している。
最近の平均処理能力、平均処理量を見ると、2006/07年度をピークに減少しており、また、工場数は、さとうきびが2年連続の不作となり操業工場数が減った2003/04年度、2004/05年度を除き、2007/08年度まで概ね増加傾向で推移し516に達したが、2008/09年度になると、さとうきび不足の影響で再び多くの工場が操業を停止し、488に減少している。
また、輸入粗糖を原料とする精製糖については、これまでごくわずかしか生産されてこなかった状況がここ数年で変わりつつあり、東海岸に精糖工場が2つ新設されたほか、西部に新たな精糖工場も建設中である。
(1)Shree Renuka社
2008年10月、ハーディア(Haldia、西ベンガル州)に、1日当たり約2,000トンの処理能力を持つ精糖工場を開業
(2)Silkroad Sugar Pvt社
Cargill社、EID Parry社は、港に本拠を置く精糖工場として、合併企業Silkroad Sugar Pvt社をカーキナーダ(Kakinada、アンドラプラデシュ州)に設立した。処理能力は現在、年間60万トンであるが、将来的に100万トンにまで増強する。製造した精製糖の再輸出先は、南アジアと東南アジアに絞るとしている。
(3)Shree Renuka社
Cargill社とEID Parry社が、ムンドラ(Mundra、グラジャート州)に2つ目の精糖工場を建設している。60万トンの生産能力を持つ見通しで、2011/12年度に操業を開始する予定である。
表4 新設・稼働予定精糖企業の生産能力
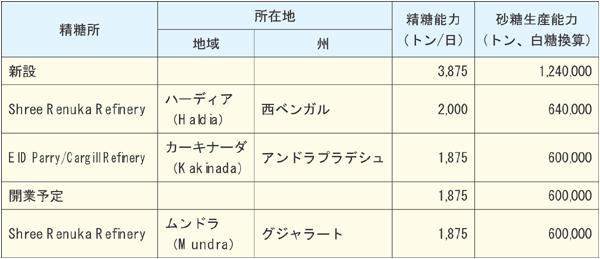
資料:LMC
(3) 砂糖の生産量
インドでは、国際砂糖分析法統一委員会(ICUMSA)基準の色価が150から400の耕地白糖が、常に生産量全体の大部分を占める。白糖は、品質(29等級、30等級、31等級)と、粒子の大きさ(小、中、大)により分類される。品質が最も低いのは29等級で、色価が高く(ICUMSA値150を大幅に上回る)、再溶糖により品質を高めている工場が多い。インドでは、ICUMSA値が100から150の30等級が最も一般的である。31等級には、ICUMSA値が50前後の質の高い砂糖が含まれる。粒子の大きさでは、小さいものがほとんどである。
また、精製糖については、既存の工場ではほとんど生産できない上、精製糖の生産量は、輸入粗糖を原料とするため、国内砂糖生産量が国内需要を満たさず政府が粗糖の輸入を許可する場合や、輸出を条件として輸入される粗糖に限定して生産されているのが現状である。
また、精製糖については、既存の工場ではほとんど生産できない上、精製糖の生産量は、輸入粗糖を原料とするため、国内砂糖生産量が国内需要を満たさず政府が粗糖の輸入を許可する場合や、輸出を条件として輸入される粗糖に限定して生産されているのが現状である。
表5 種類別砂糖生産量の推移
(単位:1,000トン、粗糖換算)
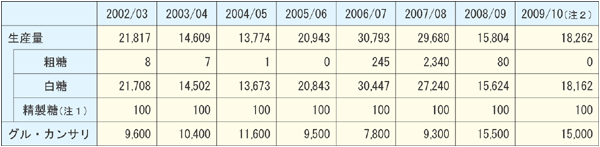
資料:LMC
注1:概算値
注2:予測値
(4) 砂糖およびグル・カンサリの消費量
砂糖消費は増加傾向となっており、家庭用が30%、業務用が70%程度で推移している。業務用部門では、飲料部門の消費量が最も多く、全体の3分の1程度を占める。飲料向けは、当初の数量が少なかったとはいえ急増しており、家庭用の需要量に近くなっており、ライフスタイルの変化による消費形態変化がみてとれる。特に、清涼飲料の需要が拡大している。
砂糖の一人当たりの年間消費量は、2002/03年度の17.7キログラムから、2009/10年度には21.3キログラム(推計)へと20%増加した。一方、グル・カンサリは、食用の消費量が徐々に低下しつつあるものの、最低が2006/07年度の6.7キロ、最高が2004/05年度の10.3キログラムとばらつきがみられる。これは、アルコール製造に使われることが多いためである。
また、インドでは、砂糖が甘味料市場の97%近くを占め、人工甘味料ではサッカリンが最も多いが、甘味料全体に占める割合は2%にすぎない。でん粉を原料とする主な甘味料では、ブドウ糖がわずか0.6%ながら一番多く、これに約0.3%のソルビトールが続く。アスパルテームも、ごく少量ながら消費されているが、異性化糖(HFS)は現在も生産されていない。
砂糖の一人当たりの年間消費量は、2002/03年度の17.7キログラムから、2009/10年度には21.3キログラム(推計)へと20%増加した。一方、グル・カンサリは、食用の消費量が徐々に低下しつつあるものの、最低が2006/07年度の6.7キロ、最高が2004/05年度の10.3キログラムとばらつきがみられる。これは、アルコール製造に使われることが多いためである。
また、インドでは、砂糖が甘味料市場の97%近くを占め、人工甘味料ではサッカリンが最も多いが、甘味料全体に占める割合は2%にすぎない。でん粉を原料とする主な甘味料では、ブドウ糖がわずか0.6%ながら一番多く、これに約0.3%のソルビトールが続く。アスパルテームも、ごく少量ながら消費されているが、異性化糖(HFS)は現在も生産されていない。
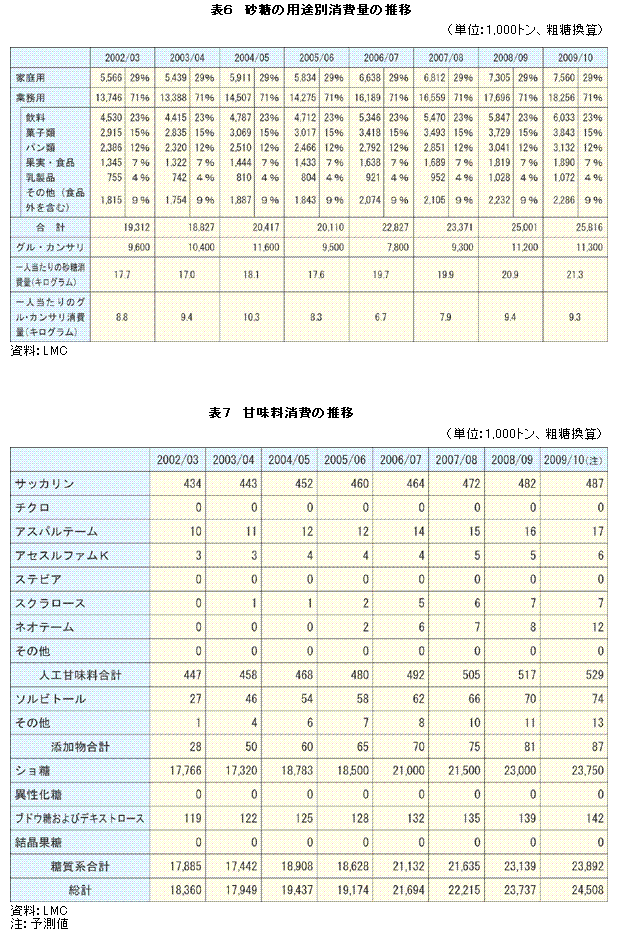
(5) 最近の状況
インドでは砂糖価格政策により、砂糖の生産量が周期的に変動(シュガーサイクル)を繰り返すため、短期的な輸入と輸出を繰り返す傾向が見られる。こうした傾向はここ数年特に目立ち、2003/04年度の大干ばつとその影響による翌年度の種苗不足により、さとうきびの生産が2年続けて不作になった。2005/06年度〜2007/08年度には一転して生産量が大幅に増加したものの、2008/09年度は国際価格が高騰した穀物への作付転換やモンスーン期の少雨により再び減少した。
輸出入の状況もこれを反映して、2003/04年度と2004/05年度には国内生産量の不足を補うため輸入が行われた。2005/06年度には砂糖の国際価格が高騰し、国内在庫がひっ迫してきたことを受け、国内価格の上昇を防ぐためインド中央政府は2006年7月に、突如、輸出を禁止した。その後、2005/06年度と2006/07年度の生産がいずれも好調であったことから、2007年1月から輸出が再開され、2006/07年度には輸出量が500万トンに達したが、2008/09年度は上述のとおり生産量が大幅に減少したため、再び輸入国に転じた。2009/10年度も主産地であるマハーラーシュトラ州およびウッタル・プラデーシュ州における降雨により生産量が前年度より増加する見込みであるものの、依然として供給不足は解消されず、600万トンの輸入が見込まれている。
輸出入の状況もこれを反映して、2003/04年度と2004/05年度には国内生産量の不足を補うため輸入が行われた。2005/06年度には砂糖の国際価格が高騰し、国内在庫がひっ迫してきたことを受け、国内価格の上昇を防ぐためインド中央政府は2006年7月に、突如、輸出を禁止した。その後、2005/06年度と2006/07年度の生産がいずれも好調であったことから、2007年1月から輸出が再開され、2006/07年度には輸出量が500万トンに達したが、2008/09年度は上述のとおり生産量が大幅に減少したため、再び輸入国に転じた。2009/10年度も主産地であるマハーラーシュトラ州およびウッタル・プラデーシュ州における降雨により生産量が前年度より増加する見込みであるものの、依然として供給不足は解消されず、600万トンの輸入が見込まれている。
表8 砂糖の需給動向
(単位:1,000トン、粗糖換算)
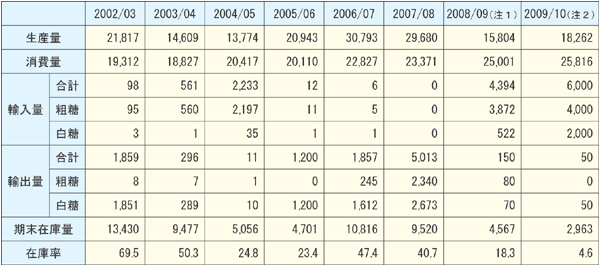
資料:ISO、LMC
注1:概算値
注2:予測値
3.砂糖政策
インドにおける砂糖政策のうち工場許可制度については、自由化が進められ、工場新設に対する規制(既存の工場から15キロ以上離して建設することを義務付け)を除き全て撤廃された。
一方、砂糖の価格政策は、さとうきび生産に対して非常に大きな影響を与えている。
さとうきび作付面積を時系列に見ると、シュガーサイクルを繰り返しながら増加傾向となっている。ISMAによれば、この主な要因は中央および州政府の砂糖価格政策にある。
製糖工場は、契約農家から中央政府が決定した価格またはSAP以上の価格で全量買い付けなければならない。さとうきびの作柄が良好となり砂糖生産量が増加して需給が緩和基調・砂糖市場価格下落となった場合には、製糖工場は砂糖市場価格に対して相対的に高いさとうきびを買い付けることになる。製糖工場は、採算ラインを越えた価格でさとうきびを農家から買い付けざるを得なくなることから、工場から農家への支払い遅延を発生させることとなり、その結果として農家は翌年の作付けを減少させる。その後、この減産により砂糖市場価格は再び上昇に転じ、製糖工場は農家へさとうきび買付金額を支払うことができるため農家は再び作付面積を増加させる。
このような、中央および州政府によるさとうきび価格制度と砂糖市場価格との不均衡が、さとうきび作付面積の基本的な変動を形成している。
近年の動向を見ると、2004/05年度は、シュガーサイクルによる作付面積の減少に加え大干ばつにより前年度に続いて不作、2005/06年度〜2007/08年度には価格回復により一転して大幅な増産、2008/09年度は、シュガーサイクルによる作付面積の減少(国際価格が高騰した穀物への作付転換など)に加えモンスーン期の少雨により大幅な減産となった。
一方、砂糖の価格政策は、さとうきび生産に対して非常に大きな影響を与えている。
さとうきび作付面積を時系列に見ると、シュガーサイクルを繰り返しながら増加傾向となっている。ISMAによれば、この主な要因は中央および州政府の砂糖価格政策にある。
製糖工場は、契約農家から中央政府が決定した価格またはSAP以上の価格で全量買い付けなければならない。さとうきびの作柄が良好となり砂糖生産量が増加して需給が緩和基調・砂糖市場価格下落となった場合には、製糖工場は砂糖市場価格に対して相対的に高いさとうきびを買い付けることになる。製糖工場は、採算ラインを越えた価格でさとうきびを農家から買い付けざるを得なくなることから、工場から農家への支払い遅延を発生させることとなり、その結果として農家は翌年の作付けを減少させる。その後、この減産により砂糖市場価格は再び上昇に転じ、製糖工場は農家へさとうきび買付金額を支払うことができるため農家は再び作付面積を増加させる。
このような、中央および州政府によるさとうきび価格制度と砂糖市場価格との不均衡が、さとうきび作付面積の基本的な変動を形成している。
近年の動向を見ると、2004/05年度は、シュガーサイクルによる作付面積の減少に加え大干ばつにより前年度に続いて不作、2005/06年度〜2007/08年度には価格回復により一転して大幅な増産、2008/09年度は、シュガーサイクルによる作付面積の減少(国際価格が高騰した穀物への作付転換など)に加えモンスーン期の少雨により大幅な減産となった。
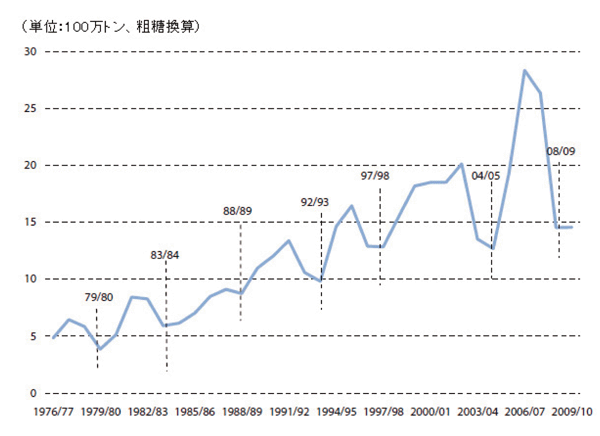
図3 インドにおける砂糖生産量の周期的変動
(1) さとうきび栽培農家政策
(1)中央政府による法定最低価格
インド中央政府は1966年から2009年まで、製糖工場が農家から買い付けるさとうきび価格SMPを設け、農家保護政策を実施していた。
SMPは、以下の事項を勘案して算定され、農家がさとうきびを植え付ける前に各州政府、砂糖産業関係者に意見を求めたうえで、農業コスト・価格委員会(CACP:Commission For Agricultural Costs And Prices)が決定し公示される。
・さとうきびの生産コスト
・代替作物栽培者および農産物価格の一般的な傾向への影響
・砂糖(価格)の消費者に対する公正性
・砂糖生産者の販売価格
・工場の砂糖回収率
インド中央政府は、2009/10年度のSMPを100キログラム当たり107.76ルピー(約2米ドル、1ルピー=0.02米ドルで換算)と決定し、さらに、工場の基準回収率が9.5%を超えると、0.1%毎に同1.13ルピーのプレミアを上乗せした価格を実質の農家買付価格としている。各製糖工場によって払うべきSMPは異なるのである。
以上のように中央政府は、さとうきびの最低価格であるSMPを定めてきたが、1955年生活必需品法(Essential Commodities Act of 1955)の改正(2009年12月)により、SMPに代わって、新たに「適正価格(F&RP:Fair and Remunerative Price)」制度が導入された。この水準を下回る価格で農家からさとうきびを仕入れることは違法となる。
F&RP制度の目的は、さとうきびの価格を全国で統一することである。2009年10月21日に公布された通知では、さとうきびのF&RPを、以下の事項を勘案し、中央政府が決定すると定めている。
・砂糖の生産コスト
・適用されるすべての租税
・製造工程で使われる資本に対する妥当な収益
すべての州に適用される2009/10年度のF&RPは、1トン当たり1,298.40ルピー(約26米ドル)に設定された(砂糖回収率9.5%を基準として、0.1%上回るごとに、1トン当たり13.7ルピーのプレミアムが支払われる)。この新制度が導入されることで、農家は、これまでのような遅延なく、代金を速やかに受け取ることができるようになるとされている。
この改正案には当初、州政府にF&RPよりも高い価格を設定することを認める一方で、工場が現在負担している差額原価を州政府に負担させる条項が新たに盛り込まれていた。これには、(ウッタル・ブラデーシュ州のように)SMPよりも高いSMPをたびたび公示する州と、そうでない州の間でみられる支払いの不平等を排除する意図があったが、強い反発を受けて、この条項案は最終的に削除された。
この結果、さとうきびの価格を設定する行政機関が2つ存在するという二重構造は残る形となった。
インド中央政府は1966年から2009年まで、製糖工場が農家から買い付けるさとうきび価格SMPを設け、農家保護政策を実施していた。
SMPは、以下の事項を勘案して算定され、農家がさとうきびを植え付ける前に各州政府、砂糖産業関係者に意見を求めたうえで、農業コスト・価格委員会(CACP:Commission For Agricultural Costs And Prices)が決定し公示される。
・さとうきびの生産コスト
・代替作物栽培者および農産物価格の一般的な傾向への影響
・砂糖(価格)の消費者に対する公正性
・砂糖生産者の販売価格
・工場の砂糖回収率
インド中央政府は、2009/10年度のSMPを100キログラム当たり107.76ルピー(約2米ドル、1ルピー=0.02米ドルで換算)と決定し、さらに、工場の基準回収率が9.5%を超えると、0.1%毎に同1.13ルピーのプレミアを上乗せした価格を実質の農家買付価格としている。各製糖工場によって払うべきSMPは異なるのである。
以上のように中央政府は、さとうきびの最低価格であるSMPを定めてきたが、1955年生活必需品法(Essential Commodities Act of 1955)の改正(2009年12月)により、SMPに代わって、新たに「適正価格(F&RP:Fair and Remunerative Price)」制度が導入された。この水準を下回る価格で農家からさとうきびを仕入れることは違法となる。
F&RP制度の目的は、さとうきびの価格を全国で統一することである。2009年10月21日に公布された通知では、さとうきびのF&RPを、以下の事項を勘案し、中央政府が決定すると定めている。
・砂糖の生産コスト
・適用されるすべての租税
・製造工程で使われる資本に対する妥当な収益
すべての州に適用される2009/10年度のF&RPは、1トン当たり1,298.40ルピー(約26米ドル)に設定された(砂糖回収率9.5%を基準として、0.1%上回るごとに、1トン当たり13.7ルピーのプレミアムが支払われる)。この新制度が導入されることで、農家は、これまでのような遅延なく、代金を速やかに受け取ることができるようになるとされている。
この改正案には当初、州政府にF&RPよりも高い価格を設定することを認める一方で、工場が現在負担している差額原価を州政府に負担させる条項が新たに盛り込まれていた。これには、(ウッタル・ブラデーシュ州のように)SMPよりも高いSMPをたびたび公示する州と、そうでない州の間でみられる支払いの不平等を排除する意図があったが、強い反発を受けて、この条項案は最終的に削除された。
この結果、さとうきびの価格を設定する行政機関が2つ存在するという二重構造は残る形となった。
表9 中央政府さとうきび法定最低価格・適正価格
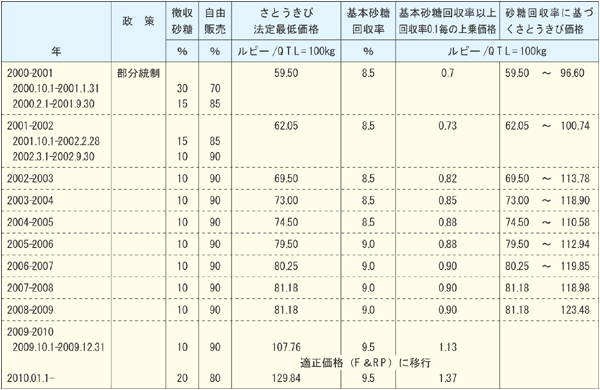
資料:ISMA「HAND BOOK of Sugar Statistics,September,2006」, LMC
(2)州政府勧告価格(SAP)
さらに、いくつかの州政府は、影響力のある農業圧力団体対策など主として政治的要因により、SMPよりも20%から30%ほど高くSAPを設定している。SAPを公示している州政府は5州で、4州が北部の産地(ウッタル・プラデーシュ州、ハリヤナ州、ウッタラーンチャル州、パンジャブ州)、残りの1州が南部の産地(タミル ナードゥ州)である。
ウッタル・プラデーシュ州のSAPは、2008/09年度では100キログラム当たり140ルピー〜145ルピーは、ハリヤナ、パンジャブ州では同140ルピー〜150ルピーである。なお、ウッタル・プラデーシュ州は、自由市場価格の上昇を背景に2009/10年度のSAPを同165ルピーと発表した。
ウッタル・プラデーシュ州のSAPは、2008/09年度では100キログラム当たり140ルピー〜145ルピーは、ハリヤナ、パンジャブ州では同140ルピー〜150ルピーである。なお、ウッタル・プラデーシュ州は、自由市場価格の上昇を背景に2009/10年度のSAPを同165ルピーと発表した。
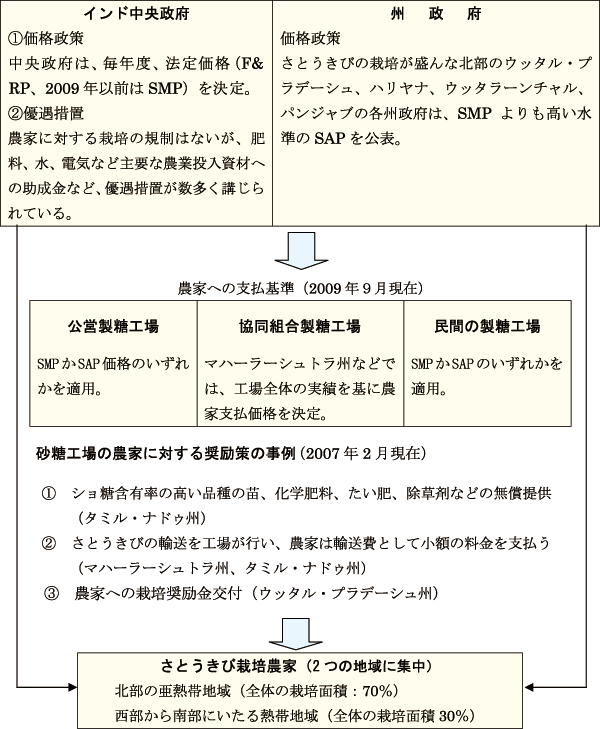
図4 さとうきびの主要政策
(2) 砂糖の国内流通政策
インド中央政府は、徴収砂糖(levy sugar)と自由販売砂糖の価格と自由販売砂糖の販売量を管理することにより、さとうきび栽培農家、砂糖生産者(製糖業者)および消費者の利益の保護と国内市場価格の安定を図っている。
(1)徴収砂糖と自由販売砂糖
その政策の一つは、徴収砂糖と呼ばれているものである。
政府は、当該年度内に国内の製糖工場で生産された砂糖のうち一定の割合について、政府が決めた価格(市場価格を下回る水準に設定された価格)で強制的に徴収する。この徴収砂糖は、製糖工場からインド食料公社(FCI:Food Corporation of India)に販売され、消費者を保護することを目的とした公共流通制度(PDS:Public Distribution System)の下で政府所有の配給店を通じて消費者に販売される。
徴収砂糖の徴収割合は、2010年になって10%から20%に引き上げられ、残りの80%は自由販売砂糖として、民間の製糖工場の場合には直接、協同組合工場の場合には全国協同組合砂糖工場連盟(NFCSF:National Federation of Co―operative Sugar Factories)を通じて、市場価格で販売される。しかし、その販売数量も政府により管理されている。
(1)徴収砂糖と自由販売砂糖
その政策の一つは、徴収砂糖と呼ばれているものである。
政府は、当該年度内に国内の製糖工場で生産された砂糖のうち一定の割合について、政府が決めた価格(市場価格を下回る水準に設定された価格)で強制的に徴収する。この徴収砂糖は、製糖工場からインド食料公社(FCI:Food Corporation of India)に販売され、消費者を保護することを目的とした公共流通制度(PDS:Public Distribution System)の下で政府所有の配給店を通じて消費者に販売される。
徴収砂糖の徴収割合は、2010年になって10%から20%に引き上げられ、残りの80%は自由販売砂糖として、民間の製糖工場の場合には直接、協同組合工場の場合には全国協同組合砂糖工場連盟(NFCSF:National Federation of Co―operative Sugar Factories)を通じて、市場価格で販売される。しかし、その販売数量も政府により管理されている。
表10 徴収砂糖価格
(単位:ルピー/kg)
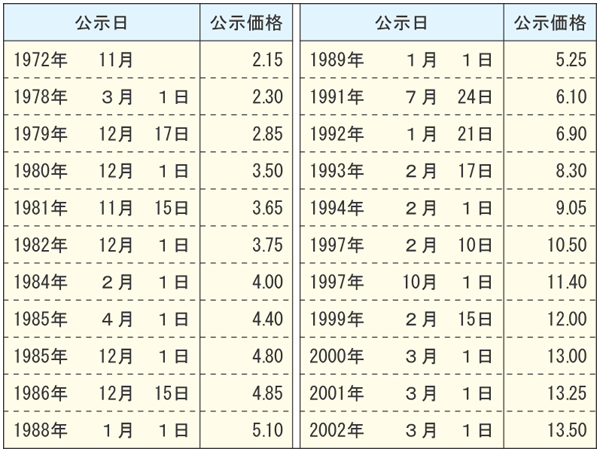
資料:ISMA「INDIAN SUGAR」
(2)自由販売砂糖における販売量の管理
自由販売砂糖は市場価格で販売されるが、販売数量については、インド消費者問題・食料・公共配給省(Ministry of Consumer Affairs,Food & Public Distribution)が毎月決めている。各地域の自由販売砂糖の価格水準を調査し、価格の低い地域は販売量を減らし、相当分を価格の高い地域へ配分することにより価格を調整している。主に州単位で調整されるが、現在、毎月の割当は、4半期に一回、事前に発表されている。
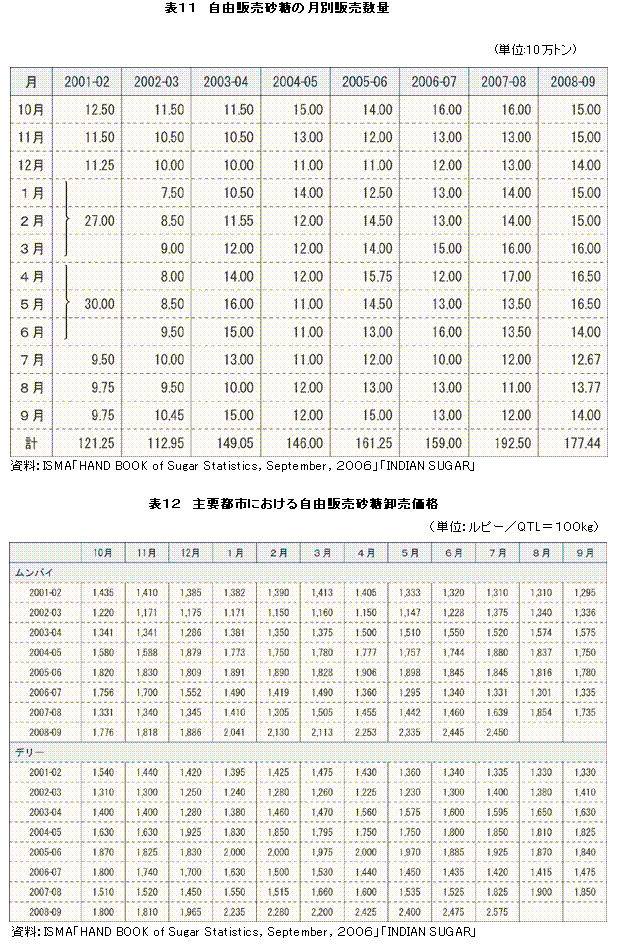
(3)グルとカンサリの保護政策
伝統的な含蜜糖であるグルとカンサリについては、比較的自由に販売される。この背景には、グル・カンサリを製造する数千の業者が伝統的に、非常に小規模にしか製造を行ってこなかったことがあり、中央政府による生産および価格政策は実施されていない。また、新設する製糖工場は既存の工場から15キロ以上離れていなければならない上、1998年9月に廃止されるまでは生産能力に対する規制も存在したのに対し、グルとカンサリの業者は既存の工場から5キロ以上離れてさえいれば、新たな工場を自由に操業できる。
砂糖の国内平均卸売価格は、概して国際価格よりも高く、輸出に対するインセンティブが小さい。唯一例外となるのは、特恵協定を結んでいるEU向けと米国向けの輸出である。この対象として輸出される砂糖は年間2万トンであるが、高水準の特恵価格の適用を受けている。
政府は、四半期ごとの販売管理制度で砂糖の価格調整を図ろうとしているが、砂糖価格は国内の生産量の過不足によって大きく変動する。インドでは国内価格がほぼ毎年国際価格を上回っているが、その価格差は輸出入の状況によって変わってくる。砂糖の国内生産量が過剰な年には、国内価格と国際価格の差が縮まり、これが不足する年には、砂糖を輸入する必要があるため、国内価格が上昇して、価格差が広がる傾向にある。
砂糖の国内平均卸売価格は、概して国際価格よりも高く、輸出に対するインセンティブが小さい。唯一例外となるのは、特恵協定を結んでいるEU向けと米国向けの輸出である。この対象として輸出される砂糖は年間2万トンであるが、高水準の特恵価格の適用を受けている。
政府は、四半期ごとの販売管理制度で砂糖の価格調整を図ろうとしているが、砂糖価格は国内の生産量の過不足によって大きく変動する。インドでは国内価格がほぼ毎年国際価格を上回っているが、その価格差は輸出入の状況によって変わってくる。砂糖の国内生産量が過剰な年には、国内価格と国際価格の差が縮まり、これが不足する年には、砂糖を輸入する必要があるため、国内価格が上昇して、価格差が広がる傾向にある。
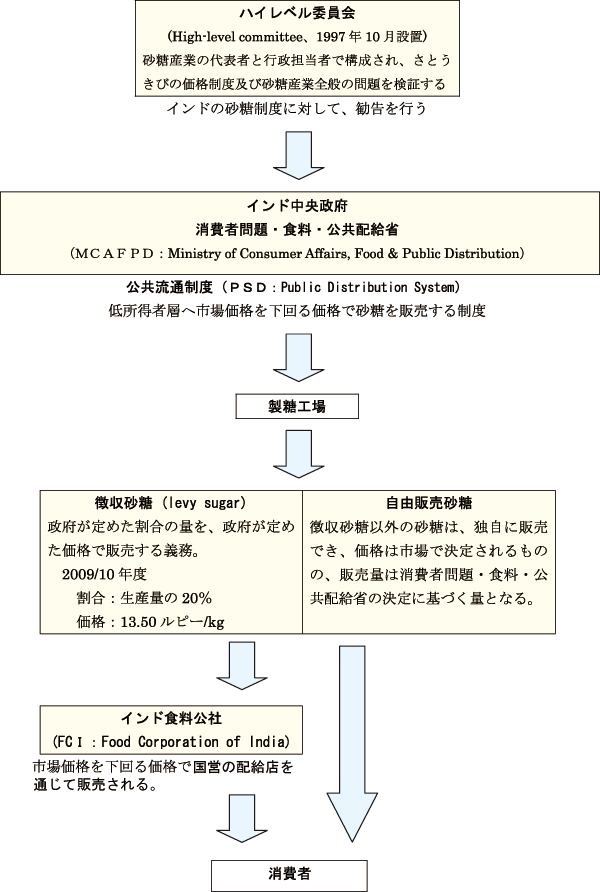
図5 さとうきびの国内流通
(3) 砂糖の輸出入政策
政府による国内価格の支持策としては、販売管理制度のほかに輸入の制限措置が挙げられる。インドは最近まで輸入粗糖と輸入白糖に60%の関税を課していたが、砂糖不足を緩和するために、2009年4月から2010年3月31日までの時限措置としてこれを免除し、2010年に入りその期限を2010年12月末まで延長した。
なお、精製後の輸出を条件に輸入される粗糖は、事前許認可制度(ALS:Advanced Licensing Scheme)により関税免除となるが、輸入粗糖1.05トンにつき、1トンの精製糖を所定の期間内に再輸出しなければならない。
なお、精製後の輸出を条件に輸入される粗糖は、事前許認可制度(ALS:Advanced Licensing Scheme)により関税免除となるが、輸入粗糖1.05トンにつき、1トンの精製糖を所定の期間内に再輸出しなければならない。
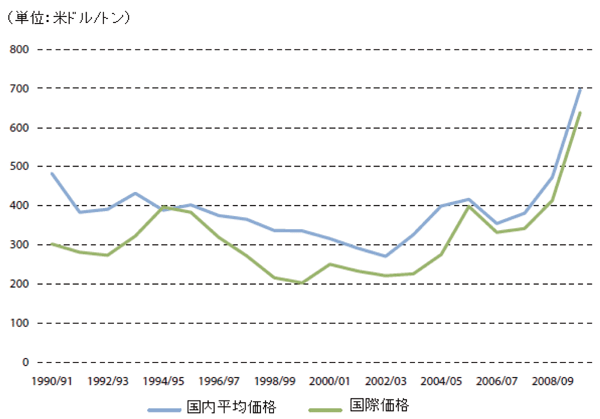
図6 白糖の国内平均価格(自由販売)と国際価格の比較
また、国内価格を調整する取り組みの一環として、政府は2009年初旬、需要の増加に鑑み、業者による買いだめを防ぐため、業者の保有在庫水準と在庫の回転を制限する時限措置を設けた。在庫の具体的な数量を定めるのは州政府であるが、中央政府は、仕入れてから1カ月以内に販売し、在庫量を常に200トン未満とするよう業者を指導した。この措置の延長が、現在検討されている。
一方、輸出においては、中央政府の国内価格を管理する取り組みの一環として、輸出数量を適宜、規制している。例えば、2006年には砂糖の国際価格が高騰し、在庫がひっ迫してきたことを受けて、国内価格の上昇を防ぐため7月に輸出禁止措置が取られた。この措置は、2005/06年度と2006/07年度のさとうきび生産が豊作となったことから、2007年1月に解除されている。
このように、砂糖の貿易においては、国内需給の安定を最優先させた規制措置が取られている。
一方、輸出においては、中央政府の国内価格を管理する取り組みの一環として、輸出数量を適宜、規制している。例えば、2006年には砂糖の国際価格が高騰し、在庫がひっ迫してきたことを受けて、国内価格の上昇を防ぐため7月に輸出禁止措置が取られた。この措置は、2005/06年度と2006/07年度のさとうきび生産が豊作となったことから、2007年1月に解除されている。
このように、砂糖の貿易においては、国内需給の安定を最優先させた規制措置が取られている。
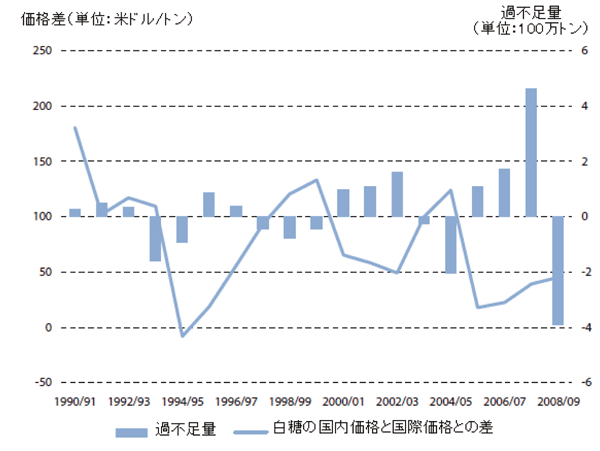
図7 国内価格と国際価格との差およびインド純輸出入量
4.エタノール生産の現状
(1) 糖みつを原料としたエタノール生産
糖みつをエタノール製造の原料に用いるブラジルを除けば、インドは世界最大の糖みつ生産量を誇っている。生産された糖みつの大半は国内で消費され、現在では90%ほどがアルコールの生産用であり、そのうち70%〜80%がアルコール飲料用、残りが工業用である。
糖みつは砂糖の製造工程で発生する副産物であるため、その生産量の増減はさとうきびの収穫量に連動する。2008/09年度には、さとうきびの不作で糖みつの生産量が450万トンも減少し、アルコールの生産量もほぼ半減した(2007/08年度22億リットル→13億リットル)。その供給不足を補うために、約4億リットルのアルコールが輸入された。
インド政府は2002/03年度から燃料用エタノールの商業生産の促進策に着手し、9つの州と4つの連邦直轄領を対象に、ガソリンへのエタノールの混合率を5%(E5)にすることを義務付ける計画を同年度に発表した。しかし、さとうきびの収穫量の増減に伴ってエタノールの生産量も変動し、供給が不安定なため一部地域における導入にとどまった。
2003/04年度のさとうきびの不作が影響してエタノールの供給が停止したことで、燃料用エタノール計画は2004年に頓挫したが、その後、砂糖と糖みつの生産が回復したことにより、2006年に19の州と8つの連邦直轄領でE5が義務付けられた。2008年には全国規模の導入も検討されたが、再び糖みつの供給不足となり、実現に至っていない。政府はその後、義務化する混合率の目標を10%(E10)に引き上げる意向を示しているものの不透明な状況が続いているもようである。
表13 糖みつ・エタノール生産の推移
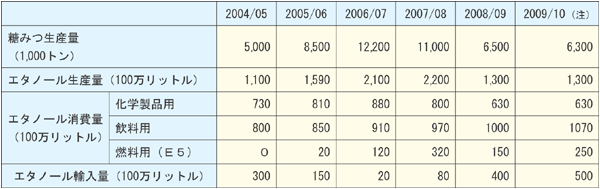
資料:LMC
注:予測値
(2) 糖みつ以外の作物を原料としたエタノール生産
一方、2007年2月の現地調査では、エタノール原料用糖みつの供給の変動を補うため、さとうもろこし(Sweet Sorghum)、熱帯シュガービート(Tropical sugar beet)、ジャトロファ(Jatropha)を原料としたエタノール生産の研究が進められていることを確認した。
さとうもろこしは、雨量が安定している中央インドのマディア・プラデーシュ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、グジャラート州の東部で栽培されているが、糖みつの不足に備え、これらの地域における大量生産体制を整備する方向であった。
熱帯シュガービートについては、米国シンジェンタ(株)から種子を導入し、マハラーシュトラ州での実証実験段階であった。熱帯シュガービートは収穫直後の加工が必要で、インフラが整っている加工工場での実証試験を予定していた。試験結果が良好であれば、アーンドラ・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、カルナータカ州における既存のさとうきび製糖工場設備の改良により、生産体制を整備する方向であった。
バイオディーゼルでは、国家計画立案委員会(Planning Commission Government of India)が2005年10月にジャトロファを原料とした計画を推進していた。自動車、トラック、大型車、鉄道ディーゼル機関車での実証試験では良好な結果を得、B5を目標に本格的な栽培が開始され、果実を収穫する2〜3年後の商業ベース利用を目指すとしていた。
インドの燃料用エタノール計画は、2008/09年度、2009/10年度におけるさとうきびの不作から、糖みつが不足して計画どおり進んでいないもようであるが、2010/11年度には砂糖の生産が回復する見込みであることに加え、コペンハーゲン合意でインドが温室効果ガスの削減を約束していること、インドでは、ガソリンよりディーゼル需要が多いことから、糖みつやジャトロファを原料とした計画が再浮上する可能性が高いと推測される。
エタノール産業における最大の問題は、政府によるエタノール価格の抑制策である。エタノール価格は、石油販売会社とエタノール工場との間の3年契約で決定され、(主原料である)糖みつの価格が高騰しても3年間にわたって据え置かれる。現在の固定価格は1リットル当たり21.5ルピー(0.45米ドル)にすぎず、エタノールの製造コストが業界の推計で(糖みつの価格を1トン当たり5,000ルピー(100米ドル)として)1リットル当たり21ルピーに上昇しているなか、生産意欲をそぐ水準といえる。ただし、2009/10年度の固定価格は、1リットル当たり26ルピー(0.54米ドル)に引き上げられ、糖みつを原料とするエタノール生産の利益が増加する見込みとなっている。
また、2007年2月の現地調査時には、産業用および燃料用エタノールは、物品税、付加価値税などの高率の税金が付加されることも問題として指摘されていた。
インドにおけるエタノール生産は、糖みつの生産変動を補う原料作物の開発・導入、エタノール価格水準、税制などの問題を抱えているが、今後の糖みつ価格の動向がエタノール生産の経済性を大きく左右するであろう。
5.砂糖産業をめぐる課題
(1) 砂糖政策
インド中央政府は、1966年から2009年まで、法定最低価格(SMP)制度を設け、農家保護政策を実施していたが、2010年から砂糖の生産コスト、適用されるすべての租税、製造工程で使われる資本に対する妥当な収益などをもととした適正価格(F&RP)制度に移行した。
この新制度が導入されることで、農家は、これまでのような代金支払いの遅延はなくなり、代金を速やかに受け取ることができるとされている。
しかし、F&RP制度においても市場価格情報が生産者に伝達されることはなく、市場メカニズムによる生産調整は期待できない。さらに、生産者が受け取るべき労働賃金等も加味された価格となるため、実質的にSMPの引き上げとなっており、製糖企業の市場価格変動リスクは大きくなっていると言える。このことから、SMP制度下で見られたシュガーサイクルはF&RP制度のもとでも継続すると推測される。 ]
F&RP制度を詳細に分析する必要があるが、製糖企業の市場価格変動リスクが大きくなる中で、制度設計どおりに農家が製糖企業から確実に代金を受け取ることが出来るとすれば、さとうきび生産者の市場価格変動によるリスクは消滅し、さとうきび生産が恒常的に過剰基調となるため、慢性的な砂糖市場価格の低迷を招く恐れもある。
しかし一方で、現在の流通制度においては、インド消費者問題・食料・公共配給省(Ministry of Consumer Affairs,Food & Public Distribution)が、国内市場における砂糖の供給量を調整していることから、概して国内平均卸売価格は国際価格よりも高く、輸出により国内供給量を調整することも難しい。
したがって、現在の流通制度やF&RP制度のもとでは、過剰在庫や国内市場価格下落などによるリスクは、基本的に製糖企業の負担において処理され、結果的に製糖企業から生産者への支払い遅延も生じる恐れがある。
F&RP制度においても、現在の価格政策に基づくシュガーサイクルはなくならないと推測され、今後、インド政府は、F&RP制度のもとでの流通政策などを再構築する必要があると思われる。
需給がタイトとなっている中で、2009/10年度における製糖企業のさとうきび買付価格は、F&RPを上回ったもようであるが、現時点では2009/10年度は砂糖生産量が前年度よりも若干増え1600万トン強になると予想されるものの、在庫が極めてひっ迫していることから、輸入量が600万トンを超える見通しである。国際砂糖の需給に大きなインパクトを与えているインドの砂糖政策の行方が注目される。
(2) 賃金上昇と労働者不足
さとうきび栽培部門では、人件費の上昇が農家を悩ませており、労働力不足への対応が大きな課題となっている。国際的にみればまだ非常に低いとはいえ、インドでも人件費は上昇しつつある。この一因としては、政府が公共事業による雇用創出で、農村地域の住民に年間100日間以上の就業を保証していることが挙げられている。農作業の大部分が手作業で行われていることを考えると、これは農家にとって大きな問題となっている。
(3) 食料需要の増加
人口増加により基本的な食料品(米、小麦、砂糖)の需要が益々高まり、これが、過去3年間にわたって法定価格を押し上げてきた。さとうきび価格と穀物(米、小麦、)価格との比較により栽培作物の転換が生じており、農地の拡大が可能な地域もあるが、さとうきび農家の平均規模が1ヘクタール未満にとどまるなか、さとうきび農家の生産性をいかに上げるのかが課題となっている。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:情報課)
Tel:03-3583-8713
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:情報課)
Tel:03-3583-8713










