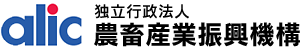�z�[�� > ���� > ���������m�� > ���O�̓`���I�ȍ��������@�i4�j
�ŏI�X�V���F2011�N10��7��
���O�̓`���I�ȍ��������@�i4�j�@�`�g�@�̍��Y������ƎF���˂̂��Ƃ����с`
2011�N10��
���a���q��w�@���ە����������@�q���������@�r������
�@�����ŁA�����̓��{�̍����̏ɂ��Ă݂Ă݂����B
�@�����ɋ�������鍻���̂قƂ�ǂ͗A���i�ŁA�u���v�Ƃ��Ĉ����Ă���A����ȋ��⓺�����̑Ή��Ƃ��Ďx����ꂽ�B�Ό���R�⍲�n���R�́A���{���������Ă������A�z�R�ɖ�����⓺�����s���ɂ���킯�ł͂Ȃ������B
�@�����̗A���i�́A��������ł͂Ȃ������B���m��w�̓������i��ł��Ȃ��������߁A��Ȗ͖ނł���A���N�l�Q��Ñ��Ȃǂ��̑������A���ɗ����Ă����B���{�́A�A���ɗ����Ă������̍��Y����ڎw���A���̎��A��Ƃ��Ė̐ݒu�ɒ��肵���B���i15�i1638�j�N�ɂ́A�������O�㏫�R�ƌ����A��ˌ�Ɩ��z����J�݂����B��ˌ�͓V�a���i1681�j�N�ɔp�~����A���̌�قǂȂ����āA�勝���N�i1684�N�j�ɖ��z������ΐ�Ɉړ]�����B���ꂪ���ΐ��̎n�܂�ł���B����6�i1721�j�N�ɁA���㏫�R�g�@�́A���ΐ������݂̏��ΐ�A�����Ƃقړ����ʐς�147,840�u�Ɋg�債���B
�@���̏��ΐ��g��̍ۂɂ́A�]�ˏ���̐�������͂��߁A���s��Ⓑ�肩����A�A���t���̂��߂̖��̎�⍪�Ȃǂ��͂����ڐA���ꂽ�B�����ŎY�o�����L�p�i�̒T���ƍ̎���s���̖�g�Ƃ��Ċe�n�֕������A
�@�̉^�c�́A���{�݂̂̂Ȃ炸�A�e�˗̂���{�m�s�n�A���Вm�s�n�Ȃǂł��������ꂽ�B���Ô˗̍ŌÂ̖Ƃ���鎭�������K�h�S�R�쒬�̎R��Ղɂ́A����̖��c���Ă���B��������炪������������サ���̂����Ȃ�����b�ł���B
�w
�@���̗������E�q��Ƃ������O���A�F���˂��牂���哇�֔h�����ꂽ�o���҂̂Ȃ��ɂȂ����ƒT���Ă݂����A������Ȃ������B�����ŁA�F���ˎm����̗ނɖ��O���łĂ��Ȃ����ƒT�����B����ł͂Ȃ����A���č]�˂̎ŁA�M�q���ɂ�������~�������̉ߋ����̒��ɁA�������E�q��̖����������B�u�F�z�ߋ����v�́A��Ƃ��Ė���3�i1657�j�N�̐U���Ύ��Ȍ�̎F���ˏo�g�҂̉ߋ����ł���B
�@�ߋ����Ȃ̂ŁA���t���ŁA���̓��t�̒��ł́A�N�����Ⴂ���ɁA���������������Ă���B�O���̂Ƃ���ɁA�u�V���Z���ߔ����@�������@�������E�q��@暓��c�K���m�v�ƁA�������E�q��̖��O��������B�V���Z�N��1786�N�ł���̂ŁA����12�N�ɕl��a�Ŏ��A�����Ƃ����59�N��ł���A�����ł������Ƃ���ΔN��I�ɂ͂��̐l���������A�F���˂��疋�{�ցA���Ƃ����т̐A���t�����w�������l���ł���ƍl������B�������A��E���u�������v�ł��������Ƃ��킩��B�ȏ�̂��Ƃ���A�]�ˎ���̓��{�ł��������������Y�ɐ����������߂��F���˂̔ˎm�ł��闎�����E�q��Ƃ����l�������݂��Ă��āA�F���˂����{�Ɏ��݂����Ƃ������������t����ꂽ�Ƃ����邾�낤�B
�@�F���˂Ƃ����ƁA���������̓Ɛ�̔��Ƃ����C���[�W�����邪�A�܂����̍��́A�⍻���́u���{���������āv�̍��Y�������āA���͂���p�����������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�ł́A�F���˂���l��a�ւ����炳�ꂽ���Ƃ����т̕i��͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��H
�@���Ƃ����тƂ����A���́A�ĂƓ����C�l�Ȃł��邪�A�c���̂悤�ɖ�����Ƃ��Ď����킯�ł͂Ȃ��B�u��v�Ƃ����ƁA�ۂ݂�тт��`��̎����C���[�W���邪�A���Ƃ����т̏ꍇ�́A�_��̌s���u��v�ł���i�ʐ^1�j�B�܂��A�������u��v�ɂȂ�B
�@����7�i1722�j�N�ɂ͖��{�̈㊯�ƂȂ�A�̒����E�������s���Ă����O�H�����́A����20�i1735�j�N�Ɋe�˂̍]�˗��狏���ĂъA�e�̓��̎Y���̒�����v�����A�G�}�t���́w�Y�����x��3�N�ԂŒ�o����悤�ɒʒB�����B�e��4����5���Ƃ��āA200�`300�̂���Ƃ���ƁA�D��1000��������{���̎Y�����ł���B�������A���{�̕����������p��������}���ق���t���ɂɂ́A���̈��w�Y�����x���[�߂��Ă��Ȃ��Ƃ����B�ǂ��֏��������͓�ł���B�������A��o����˂́A�T�����Ƃ��Ă���͂��Ȃ̂ŁA���ꂪ�A�����I�Ɏc���Ă���˂�����B
�@�����ŁA�F���˂̎Y�����ɁA���Ƃ����т��`����Ă��Ȃ����ƍl�����B
�@���̂���F���˂́A�������A������A�F������̂��Ă���A�����̍��̎Y�����̍T���̈ꕔ���`�����Ă���B
�@�������Y�ɐ������Ă��������哇�A��E���A���V���Ȃǂ́A�F�����̂������̂ŁA���Ƃ����т��`����Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��̂����A�c�O�Ȃ���A�F�����̕��́A�{���������Ă���G�}�������c���Ă�����̂́A����������̂ŁA���{�֒�o�����Y�����ɂ��Ƃ����т��ڂ����Ă����̂��ۂ��킩��Ȃ��B
�@�������A�Y�������쐬����ɂ������āA�F���˂̍]�˗��狏���A�O�H�����Ɏf�������Ă����̋L�^���c���Ă���B����ɂ��ƁA�����̎Y���͏��O���Ă������ƁA�܂���������n�����ė̓��Ő��炵�Ă���Y�������O���Ă����Ƃ̕ԓ��ł������B���������āA���������ɗ�������ڐA���ꂽ���Ƃ����т́A���������`����Ă��Ȃ������\���������B

�@
�@���̎Y�����̒�o�����30�N��̖��a5�i1768�j�N�A�F���ˎ哇�Ïd���́A�F�쏔���̓��E�A���̕W�{�̍̎�ƒ�o�����߂��B2�N��̖��a7�N�ɁA�W�߂�ꂽ�A���̕W�{�́A�{���w�҂ň�t�̍��o�i�c�����Y�j�֓n����A�����Ƃ̓���������c���Ɉ˗����ꂽ�B���N�A�w�����Y���u�x�Ƃ��āA�ʐF�}�ƒ��L�t����15�����^3���̌v18���Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ�B�u�����v�Ƒ肷����̂́A��ȎY�n�͉����哇�i�����哇�j�Ƃ���A���ɗ������A�g�J�����A�F���ȂǂŁA��730�i�����̎F�쏔���̐A�����ł���B���̂Ȃ��ɁA���Ƃ����т��������̂��B�u����v�Ɓu������(������)�v�Ƃ������O�ŁA2��ނ��`����Ă���i�ʐ^2�j�i�ʐ^3�j�B
�@�u����v�̒��L�ɂ́A�u�o�A�s������ځA���t���O�ڌv�A?�s�`���B��?�L�p�@�����y����?�G�v�Ƃ���A�s������ď`������č����ɂ�����@������Ƃ��Ă���B
�@����u������v�̒��L�ɂ́A�u�{������L�ԐF�Җ�������A�o�䉬�s�t���厧�ԐF���߁@�����y���^���A�F�B�퓇�������o���v�Ƃ���A�����̖�w���ł���w�{���j�ځx�ɁA�Ԃ��F������̂͛�����Ɩ������邱�Ƃ��Љ��A��������s�Ɨt���傫���A�߂ɐԐF�������Ƃ����������L����Ă���B
�@���۔N�Ԃɕl��a�֎��A���ꂽ�̂́A����̂��Ƃ����сA���邢�͈���̂��Ƃ����тł͂Ȃ��������I�H
�@�����̂��Ƃ����т��������Ă��Ȃ����A�ʐF�}�ɂ���āA�]�˂֎��A���ꂽ���Ƃ����т̎p��z�����邵���p�͂Ȃ����A����ł��`���ꂽ���̂��c���Ă��Ă悩�����B
�@���̍��̖E�{���E�Y���w�𐄐i�A�������ꂽ��l��ցA����������v���ł���B
�@�u����v�̒��L�ɂ́A�u�o�A�s������ځA���t���O�ڌv�A?�s�`���B��?�L�p�@�����y����?�G�v�Ƃ���A�s������ď`������č����ɂ�����@������Ƃ��Ă���B
�@����u������v�̒��L�ɂ́A�u�{������L�ԐF�Җ�������A�o�䉬�s�t���厧�ԐF���߁@�����y���^���A�F�B�퓇�������o���v�Ƃ���A�����̖�w���ł���w�{���j�ځx�ɁA�Ԃ��F������̂͛�����Ɩ������邱�Ƃ��Љ��A��������s�Ɨt���傫���A�߂ɐԐF�������Ƃ����������L����Ă���B
�@���۔N�Ԃɕl��a�֎��A���ꂽ�̂́A����̂��Ƃ����сA���邢�͈���̂��Ƃ����тł͂Ȃ��������I�H
�@�����̂��Ƃ����т��������Ă��Ȃ����A�ʐF�}�ɂ���āA�]�˂֎��A���ꂽ���Ƃ����т̎p��z�����邵���p�͂Ȃ����A����ł��`���ꂽ���̂��c���Ă��Ă悩�����B
�@���̍��̖E�{���E�Y���w�𐄐i�A�������ꂽ��l��ցA����������v���ł���B
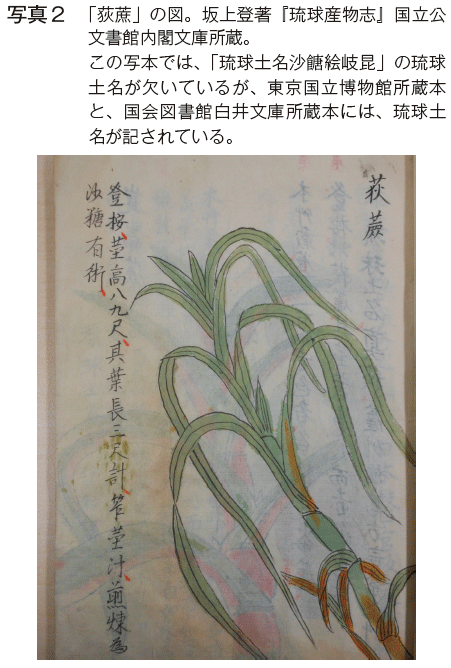
�@

�@
���̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă�����̔��M��
�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j
Tel:03-3583-8678
�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j
Tel:03-3583-8678