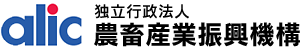ホーム > 砂糖 > お砂糖豆知識 > 内外の伝統的な砂糖製造法(13)
最終更新日:2012年7月10日
内外の伝統的な砂糖製造法(13)
〜江戸時代の朱印船貿易、そして現代のベトナム〜
2012年7月
昭和女子大学国際文化研究所 客員研究員 荒尾 美代
日本とベトナムとの貿易は、早くも秀吉の時代から行われていた。日本から東南アジアへ船を仕立て、海外貿易を行うようになり、渡海許可証である「御朱印状」が必要であったので、「朱印船貿易」と呼ばれている。しかし、盛んになるのは、家康の時代からである。
関ヶ原の合戦の翌年である慶長6(1601)年夏に、ベトナム中部を支配していた阮( グエン)氏の「国書」を携えた商船が日本へやってきた。家康は同年10月に返書と武具を贈った。翌年の6月には、1200人もの人間を乗せたベトナム船が長崎に入津し、生きた虎、象、孔雀を家康に贈った。慶長6年から11年までは、毎年ベトナムから商船がやってきている。もちろん、奉書と献上品も携えて・・・・。慶長15年の献上物の中に、鸚鵡 と、孔雀、沈香 という香木などにならんで、氷砂糖と思われるものが10壺ある。
このように、江戸時代初期にはベトナムと日本は親交が密であり、貿易も盛んであった。
伊勢神宮の近くの大湊を本拠地にし、後に松坂の港町に移った回船業を主とする角屋家にベトナムと貿易していた商人がいた。この角屋家は、信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」の直後、家康が三河まで帰るのを船で助けたとして、家康から角屋船の三河・遠江諸港への出入の諸税の免除した免許状を発給された。のちに家康が天下を取ると、諸国港出入自由諸役免除の御朱印を授けられ、その慣例は、江戸時代を通じて踏襲された。
家康の窮地を救った角屋七郎次郎秀持の次男、七郎兵衛栄吉は、角屋の御朱印船八幡丸に乗って、寛永8(1631)年、ベトナムに向かった。栄吉は、ベトナム中部のホイアンに移住して、他の邦人たちと日本人町をつくった。当時のホイアンは、日本からの御朱印船、「唐船」、オランダ船、ポルトガル船も来港する国際貿易都市だった。
七郎兵衛がベトナムへ移住して2年後、寛永10年から幕府は徐々に鎖国への道をたどるようになった。この時幕府が発した統制令は、海外にいる日本人は5年以内に帰国すること、それ以後の帰国は死罪とするというものだった。さらに2年後の寛永12年には、日本の船は一切異国へ行ってはならない、異国にいる者は帰国してはならないと発布した。
寛永16年には、キリスト教の布教を行ってきたポルトガル船の来航を禁止し、オランダ船と「唐船」による貿易しか許されなくなり、日本から手紙を出すこともかなわなかった。
さて、日本に戻ることができない七郎兵衛は、阮氏の娘を妻とし、順官という息子をもうけている。
その後、寛文年間に、通信の許可がおり、寛文6(1666)年6月の日付で、ベトナムに渡った七郎兵衛から、松坂在住の兄・七郎次郎(代々七郎次郎を名乗る)と、堺在住の弟・九郎兵衛宛に出された手紙の写しが、伊勢神宮の神宮徴古館所蔵の『安南記』に所収されている。
書簡の中で七郎兵衛は、七郎次郎と九郎兵衛に、長崎まで行って、長崎在住の角屋家の親戚である荒木久右衛門から、「唐船」の船頭や船員、そして商客ら合計5人に貸し付けている銀を受け取るように要請している。すなわち、ベトナムで商品を購入し、日本へ持って行って売ろうとしている彼らに、七郎兵衛は銀をベトナムで貸しているのである。
その銀で仕入れを行った船頭らは、長崎で商品を売り、七郎兵衛からベトナムで借りた銀を、久右衛門に返すという約束で借り請けていた。その貸し付け合計は、丁銀(秤量して流通した海鼠形の銀貨)40貫目であった。
そして、この書簡には、大量の白砂糖を送ったことが記されている。これらの白砂糖も、久右衛門から受け取るように指示している。文脈から、銀を貸した船頭や商客が乗った船3艘と、別の船1艘に舶載されて日本へ運ばれたと考えられる。その量は合計で約500斤、すなわち約300キログラムもの白砂糖が、七郎兵衛の兄弟2人へ送られたのだ。
七郎兵衛は、ホイアンで白砂糖を購入し、それぞれの船頭の船に舶載して、長崎まで届けてもらったものと考えられる。
寛文10(1770)年5月の日付のある、ベトナムの七郎兵衛から長崎の荒木勘左衛門と荒木久左衛門宛の書簡の写しもある。それには、大量の黒砂糖を各人へ贈る旨が記されている。原文をそのまま記すと、
関ヶ原の合戦の翌年である慶長6(1601)年夏に、ベトナム中部を支配していた阮( グエン)氏の「国書」を携えた商船が日本へやってきた。家康は同年10月に返書と武具を贈った。翌年の6月には、1200人もの人間を乗せたベトナム船が長崎に入津し、生きた虎、象、孔雀を家康に贈った。慶長6年から11年までは、毎年ベトナムから商船がやってきている。もちろん、奉書と献上品も携えて・・・・。慶長15年の献上物の中に、
このように、江戸時代初期にはベトナムと日本は親交が密であり、貿易も盛んであった。
伊勢神宮の近くの大湊を本拠地にし、後に松坂の港町に移った回船業を主とする角屋家にベトナムと貿易していた商人がいた。この角屋家は、信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」の直後、家康が三河まで帰るのを船で助けたとして、家康から角屋船の三河・遠江諸港への出入の諸税の免除した免許状を発給された。のちに家康が天下を取ると、諸国港出入自由諸役免除の御朱印を授けられ、その慣例は、江戸時代を通じて踏襲された。
家康の窮地を救った角屋七郎次郎秀持の次男、七郎兵衛栄吉は、角屋の御朱印船八幡丸に乗って、寛永8(1631)年、ベトナムに向かった。栄吉は、ベトナム中部のホイアンに移住して、他の邦人たちと日本人町をつくった。当時のホイアンは、日本からの御朱印船、「唐船」、オランダ船、ポルトガル船も来港する国際貿易都市だった。
七郎兵衛がベトナムへ移住して2年後、寛永10年から幕府は徐々に鎖国への道をたどるようになった。この時幕府が発した統制令は、海外にいる日本人は5年以内に帰国すること、それ以後の帰国は死罪とするというものだった。さらに2年後の寛永12年には、日本の船は一切異国へ行ってはならない、異国にいる者は帰国してはならないと発布した。
寛永16年には、キリスト教の布教を行ってきたポルトガル船の来航を禁止し、オランダ船と「唐船」による貿易しか許されなくなり、日本から手紙を出すこともかなわなかった。
さて、日本に戻ることができない七郎兵衛は、阮氏の娘を妻とし、順官という息子をもうけている。
その後、寛文年間に、通信の許可がおり、寛文6(1666)年6月の日付で、ベトナムに渡った七郎兵衛から、松坂在住の兄・七郎次郎(代々七郎次郎を名乗る)と、堺在住の弟・九郎兵衛宛に出された手紙の写しが、伊勢神宮の神宮徴古館所蔵の『安南記』に所収されている。
書簡の中で七郎兵衛は、七郎次郎と九郎兵衛に、長崎まで行って、長崎在住の角屋家の親戚である荒木久右衛門から、「唐船」の船頭や船員、そして商客ら合計5人に貸し付けている銀を受け取るように要請している。すなわち、ベトナムで商品を購入し、日本へ持って行って売ろうとしている彼らに、七郎兵衛は銀をベトナムで貸しているのである。
その銀で仕入れを行った船頭らは、長崎で商品を売り、七郎兵衛からベトナムで借りた銀を、久右衛門に返すという約束で借り請けていた。その貸し付け合計は、丁銀(秤量して流通した海鼠形の銀貨)40貫目であった。
そして、この書簡には、大量の白砂糖を送ったことが記されている。これらの白砂糖も、久右衛門から受け取るように指示している。文脈から、銀を貸した船頭や商客が乗った船3艘と、別の船1艘に舶載されて日本へ運ばれたと考えられる。その量は合計で約500斤、すなわち約300キログラムもの白砂糖が、七郎兵衛の兄弟2人へ送られたのだ。
七郎兵衛は、ホイアンで白砂糖を購入し、それぞれの船頭の船に舶載して、長崎まで届けてもらったものと考えられる。
寛文10(1770)年5月の日付のある、ベトナムの七郎兵衛から長崎の荒木勘左衛門と荒木久左衛門宛の書簡の写しもある。それには、大量の黒砂糖を各人へ贈る旨が記されている。原文をそのまま記すと、
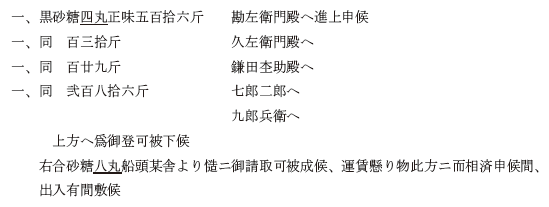
ここで注目したいのは、筆者が下線を引いた「四丸」「八丸」という「丸」の単位である。
4丸が約516斤としているので、1丸が約129斤となる。1斤は600グラムなので、約77キログラムである。次の久左衛門へは130斤、鎌田杢助へは129斤なので、先に割り出した1丸の単位の斤数に近い。七郎二郎と九郎兵衛へは286斤であるが、これが2丸とすると、合計8丸となる。
このベトナムの砂糖の「丸」の単位と考えられる具体的な様相のことを、江戸時代中期にベトナムに漂着した日本人が記している。少々長くなるが、この漂着民について記したい。
明和2(1765)年10月に常陸国磯原村から出帆した船が、陸奥国小名浜で米を積んで同月28日に銚子に着き、積米を渡した後帰国途中に遭難し、12月17日にベトナムに漂着した。一方、同年11月3日に米を積んで小名浜から出帆した船も銚子を目指したが遭難し、翌年1月25日にベトナムに漂着した。磯原村の生存者4名、小名浜村の生存者3名は、ベトナムで仕入れを行った「唐船」によって、明和4年7月16日に、無事長崎へ送り届けられた。
日本に帰った彼らが話した遭難から漂着、そしてベトナムでの様子の記録が残されている。
ベトナムに漂着した2つの船の乗組員は、最終的にホイアンに連れてこられ、この地に滞在した。当時のホイアンは、かつて七郎兵衛が生きたていた時代から引き続き、国際貿易都市であった。
この漂着民が、竹を剥いで、箕笊 のごとくに作った俵に、氷砂糖と白砂糖を入れる様子を目撃しているのだ。この俵に砂糖を入れるときは、庭に砂糖を山のように出し並べて、俵へ入るだけ入れて杵で突き込むとしている。またこの俵は、日本の「五斗俵」程の大きさに作るとしている。「五斗俵」は、米1斗が約15キログラムなので、5斗だと75キログラム入り位の大きさの、編んだ容器を漂着民が目撃したと思われる。
先に見たように、七郎兵衛がベトナムから、日本へ送った黒砂糖「一丸」の重量も、77キログラム前後と考えられるので、「一丸」は「五斗俵」に入った一括りの単位とみていいだろう。
そして、日本人の漂着民が乗った「唐船」にも、2000俵もの砂糖を積み、また、その他17−18艘の南京船すべてが、砂糖を買って積み込んでいたとしている。この漂着民は、「ベトナムの産物は砂糖第一」と言っている。それほど、砂糖は中心的な貿易品だったのであろう。
このように、日本でまだ砂糖の国産化が成功しない江戸時代中期頃までは、ベトナム産の砂糖が、大量に日本へ舶載されていたと考えられる。
さらに、その漂着民らがベトナムから乗ったと思われる船が資料の中に見つかった。
ベトナムへ漂着した日本人を連れて帰った「唐船」は、明和4年6月20日にホイアンを出航し、どこへも立ち寄らず、直接長崎に入津。その日付は、同年7月16日である。
オランダ人は、長崎のオランダ通詞(注1)を通じて、こっそり唐船の積荷リストの情報をもらっていた。オランダ人にとっては、「唐船」は、貿易のライバルだったので、どんな商品をどの位仕入れ、売値などの情報は、まさに喉から手が出るほど欲しかったことは想像に難くない。それらの情報が、商館日記などに残されている。「唐船」による貿易の取引額などを直接示す史料が乏しいので、オランダ側が入手した情報は、大変貴重であるのだ。
(注1)江戸時代、オランダとの交渉にあたった通訳。
オランダ人が記す日付というのは、グレゴリオ歴(西暦)なので、日本人が記す和暦とは異なる。インターネットで、和暦と西暦の日付まで換算してくれるサイトで、ベトナムから漂着民が長崎に入津した日付である和暦の明和4年7月16日を入力して換算すると、西暦 1767年 8月 10日となった。この日が西暦の長崎入津日である。
しかし、積荷目録は入津日よりも後の日付の条に記載されることが多いという。また「唐船」がどこの船かを言う場合、船籍ではなく、仕入れを行った出港地で言われるようにもなった。したがって、船籍が他国のどこかの地であっても、ベトナムの船として記録されている可能性がある。 永積洋子氏の『唐船輸出入品数量一覧1637-1833年』(創文社1987年)は、オランダ側に残されている(もちろんオランダ語で記されている)商館日記などの文書から、「唐船」の輸出入商品に関する記事を抽出して、そもそもは唐通事 (注2)によって日本語にされた積荷目録を復元したものである。
さて、西暦 1767年8月10日以降のオランダ側が得ていた「唐船」の積荷リストを永積氏の本から探してみると、なんと、西暦1767年8月14日条に4番交趾(ベトナム中部)船の積荷の情報が出ていたのである。
これには、氷砂糖第一種61120斤、氷砂糖第二種168000斤、最上白砂糖8960斤、白砂糖第二種79680斤、砂糖菓子三種44667斤、黒砂糖29890斤、その他、唐寺用として白砂糖2俵が舶載されていた。
このベトナム船に、大量の砂糖と共に、漂着民が乗っていたのではないだろうか。
(注2)江戸時代、中国との貿易交渉にあたった通訳
さて、現代のベトナムも砂糖天国といって過言ではないだろう。かつて七郎兵衛が骨を埋め、また、日本人漂着民も滞在したベトナム中部の砂糖について報告することにしよう。少々データは古いが、1999年3月に調査を行った、伝統的な氷砂糖の作り方を紹介したい。
まずは、その概要から。
現在は、ミルで作られるグラニュー糖を使用。グラニュー糖1袋50キログラム入りで、当時の値段は、1キロあたり5800ドン(表記:D)で入荷し、氷砂糖を作って、1キロあたり7400Dで売る。結晶を成長させるスチール製(1990年までは素焼き)の容器には、1つあたり150キログラムのグラニュー糖を使用する。氷砂糖を作る際に出る、細かい結晶も使用する。これから、氷砂糖約80キログラムと、蜜が40リットル得られる。蜜は、ビスケットやアイスクリーム製造業者に売る。売値は1リットルにつき5100D。
早朝3時から夕方6時までの間で、11個の容器を満たす糖液を作る。氷砂糖が出来るのは1週間後である。
次に製造工程を記す。
1.グラニュー糖50キログラムにつき約20リットルの水を入れて鍋にかけ、加熱する。
2.卵3個を溶いて鍋にいれる。
3.浮上してくる不純物を取り除く。
4.吹きこぼれそうになると、少量の水を加える。
5.布で漉し(写真1)、再び高温で加熱する。
4丸が約516斤としているので、1丸が約129斤となる。1斤は600グラムなので、約77キログラムである。次の久左衛門へは130斤、鎌田杢助へは129斤なので、先に割り出した1丸の単位の斤数に近い。七郎二郎と九郎兵衛へは286斤であるが、これが2丸とすると、合計8丸となる。
このベトナムの砂糖の「丸」の単位と考えられる具体的な様相のことを、江戸時代中期にベトナムに漂着した日本人が記している。少々長くなるが、この漂着民について記したい。
明和2(1765)年10月に常陸国磯原村から出帆した船が、陸奥国小名浜で米を積んで同月28日に銚子に着き、積米を渡した後帰国途中に遭難し、12月17日にベトナムに漂着した。一方、同年11月3日に米を積んで小名浜から出帆した船も銚子を目指したが遭難し、翌年1月25日にベトナムに漂着した。磯原村の生存者4名、小名浜村の生存者3名は、ベトナムで仕入れを行った「唐船」によって、明和4年7月16日に、無事長崎へ送り届けられた。
日本に帰った彼らが話した遭難から漂着、そしてベトナムでの様子の記録が残されている。
ベトナムに漂着した2つの船の乗組員は、最終的にホイアンに連れてこられ、この地に滞在した。当時のホイアンは、かつて七郎兵衛が生きたていた時代から引き続き、国際貿易都市であった。
この漂着民が、竹を剥いで、
先に見たように、七郎兵衛がベトナムから、日本へ送った黒砂糖「一丸」の重量も、77キログラム前後と考えられるので、「一丸」は「五斗俵」に入った一括りの単位とみていいだろう。
そして、日本人の漂着民が乗った「唐船」にも、2000俵もの砂糖を積み、また、その他17−18艘の南京船すべてが、砂糖を買って積み込んでいたとしている。この漂着民は、「ベトナムの産物は砂糖第一」と言っている。それほど、砂糖は中心的な貿易品だったのであろう。
このように、日本でまだ砂糖の国産化が成功しない江戸時代中期頃までは、ベトナム産の砂糖が、大量に日本へ舶載されていたと考えられる。
さらに、その漂着民らがベトナムから乗ったと思われる船が資料の中に見つかった。
ベトナムへ漂着した日本人を連れて帰った「唐船」は、明和4年6月20日にホイアンを出航し、どこへも立ち寄らず、直接長崎に入津。その日付は、同年7月16日である。
オランダ人は、長崎のオランダ通詞(注1)を通じて、こっそり唐船の積荷リストの情報をもらっていた。オランダ人にとっては、「唐船」は、貿易のライバルだったので、どんな商品をどの位仕入れ、売値などの情報は、まさに喉から手が出るほど欲しかったことは想像に難くない。それらの情報が、商館日記などに残されている。「唐船」による貿易の取引額などを直接示す史料が乏しいので、オランダ側が入手した情報は、大変貴重であるのだ。
(注1)江戸時代、オランダとの交渉にあたった通訳。
オランダ人が記す日付というのは、グレゴリオ歴(西暦)なので、日本人が記す和暦とは異なる。インターネットで、和暦と西暦の日付まで換算してくれるサイトで、ベトナムから漂着民が長崎に入津した日付である和暦の明和4年7月16日を入力して換算すると、西暦 1767年 8月 10日となった。この日が西暦の長崎入津日である。
しかし、積荷目録は入津日よりも後の日付の条に記載されることが多いという。また「唐船」がどこの船かを言う場合、船籍ではなく、仕入れを行った出港地で言われるようにもなった。したがって、船籍が他国のどこかの地であっても、ベトナムの船として記録されている可能性がある。 永積洋子氏の『唐船輸出入品数量一覧1637-1833年』(創文社1987年)は、オランダ側に残されている(もちろんオランダ語で記されている)商館日記などの文書から、「唐船」の輸出入商品に関する記事を抽出して、そもそもは
さて、西暦 1767年8月10日以降のオランダ側が得ていた「唐船」の積荷リストを永積氏の本から探してみると、なんと、西暦1767年8月14日条に4番交趾(ベトナム中部)船の積荷の情報が出ていたのである。
これには、氷砂糖第一種61120斤、氷砂糖第二種168000斤、最上白砂糖8960斤、白砂糖第二種79680斤、砂糖菓子三種44667斤、黒砂糖29890斤、その他、唐寺用として白砂糖2俵が舶載されていた。
このベトナム船に、大量の砂糖と共に、漂着民が乗っていたのではないだろうか。
(注2)江戸時代、中国との貿易交渉にあたった通訳
さて、現代のベトナムも砂糖天国といって過言ではないだろう。かつて七郎兵衛が骨を埋め、また、日本人漂着民も滞在したベトナム中部の砂糖について報告することにしよう。少々データは古いが、1999年3月に調査を行った、伝統的な氷砂糖の作り方を紹介したい。
まずは、その概要から。
現在は、ミルで作られるグラニュー糖を使用。グラニュー糖1袋50キログラム入りで、当時の値段は、1キロあたり5800ドン(表記:D)で入荷し、氷砂糖を作って、1キロあたり7400Dで売る。結晶を成長させるスチール製(1990年までは素焼き)の容器には、1つあたり150キログラムのグラニュー糖を使用する。氷砂糖を作る際に出る、細かい結晶も使用する。これから、氷砂糖約80キログラムと、蜜が40リットル得られる。蜜は、ビスケットやアイスクリーム製造業者に売る。売値は1リットルにつき5100D。
早朝3時から夕方6時までの間で、11個の容器を満たす糖液を作る。氷砂糖が出来るのは1週間後である。
次に製造工程を記す。
1.グラニュー糖50キログラムにつき約20リットルの水を入れて鍋にかけ、加熱する。
2.卵3個を溶いて鍋にいれる。
3.浮上してくる不純物を取り除く。
4.吹きこぼれそうになると、少量の水を加える。
5.布で漉し(写真1)、再び高温で加熱する。

6.小皿に入れた水に糖液を垂らし、取り上げるタイミングをみる。
7.上部と下部を円形に竹で編み、その間に沢山の糸を吊したもの(写真2)をバケツ様のスチール容器の中に入れ、その中に糖液を入れる。
7.上部と下部を円形に竹で編み、その間に沢山の糸を吊したもの(写真2)をバケツ様のスチール容器の中に入れ、その中に糖液を入れる。

8.1週間後、容器の上部竹編み部分にも、結晶が析出しているのが確認できる(写真3)。
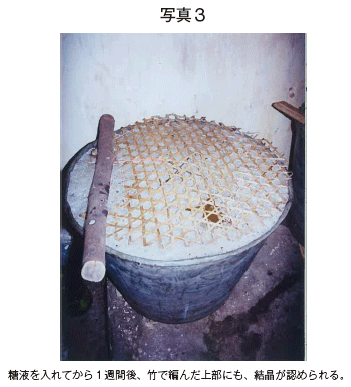
9.容器を傾け、非結晶部分の蜜を別の容器で受け入れる。
10.容器から氷砂糖の塊を取り出し、ハンマーで割る(写真4)。
10.容器から氷砂糖の塊を取り出し、ハンマーで割る(写真4)。

11.容器の内壁部には分厚く、糸の部分は氷柱のように細長く結晶が成長している(写真5)。
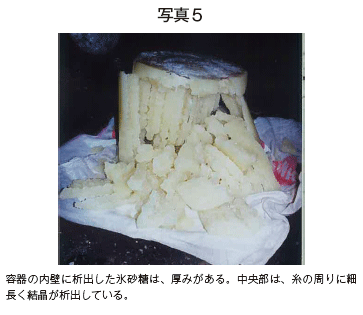
12.これらをそれぞれ砕く(写真6)。

13.1日日光に当てて乾かす(写真7)。

原料とする砂糖のクオリティは違っても、何百年も前から砂糖生産地として名を馳せていたことが想像できる光景が、まだベトナムにはあった。
最後に、今一度、江戸時代の角屋家の話に戻りたい。
私事で恐縮だが、角屋家の文書の中に、私の先祖で、江戸時代前期に2代将軍秀忠によって旗本に取り立てられた荒尾平八郎が、松坂の角屋七郎次郎に宛てた書簡の直筆が、伊勢神宮の神宮徴古館と名古屋大学付属図書館に所蔵されている。十数年前に、重要文化財に指定されている神宮徴古館所蔵の角屋家の書簡集を閲覧させていただいた。先祖の直筆に対面した瞬間だった。ベトナムの砂糖を確かに受け取っていた七郎次郎と親しかった私の先祖のことを知り、「(平八郎は)ベトナムの砂糖をもらって食べていたかもしれない・・・」と、感慨深いものがあった。
最後に、今一度、江戸時代の角屋家の話に戻りたい。
私事で恐縮だが、角屋家の文書の中に、私の先祖で、江戸時代前期に2代将軍秀忠によって旗本に取り立てられた荒尾平八郎が、松坂の角屋七郎次郎に宛てた書簡の直筆が、伊勢神宮の神宮徴古館と名古屋大学付属図書館に所蔵されている。十数年前に、重要文化財に指定されている神宮徴古館所蔵の角屋家の書簡集を閲覧させていただいた。先祖の直筆に対面した瞬間だった。ベトナムの砂糖を確かに受け取っていた七郎次郎と親しかった私の先祖のことを知り、「(平八郎は)ベトナムの砂糖をもらって食べていたかもしれない・・・」と、感慨深いものがあった。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678