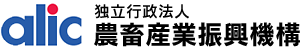ホーム > 砂糖 > お砂糖豆知識 > 内外の伝統的な砂糖製造法(20)
最終更新日:2013年2月12日
内外の伝統的な砂糖製造法(20)
〜日本の伝統技術にみる「覆土法」から「加圧法」へ―日本人の砂糖の嗜好〜
2013年2月
昭和女子大学 国際文化研究所 客員研究員 荒尾 美代
2012年5月号で、幕府が寛政9年に『砂糖製作記』という刊本まで出して、積極的に砂糖製造を推進したということを書いた。この中で、幕府が推進していた砂糖製造法は、植木鉢のように底に穴が開けられた容器「瓦漏」の中に、まずその穴を塞いだ上でさとうきびジュースを煮詰めた濃縮糖液を入れて結晶化を待ち、その後穴の塞ぎを取り除き、非結晶分である黒い蜜(モラセス)を重力によって下に落とすという第一の分蜜法を採るものであった。その後に行うのが、「瓦漏」の中で半固化している砂糖の塊の上部に、水分を含んだ土を乗せて第二の分蜜を施す「覆土法」だ。
土を使うという、摩訶不思議な方法。
覆土の効果は、土に含まれる水分の滴下によって、結晶の周りに存在している黒い蜜を洗い流す他に、覆土が乾いた時に、毛管現象によって覆土側に蜜が上昇して分蜜もされるという新たな知見を得たことを2012年3月号と5月号で紹介した。
近年、考古学の発掘調査の成果から、植木鉢様の「瓦漏」が日本で出土している。この容器を見て、砂糖製造に使う「瓦漏」では?と最初に着想したのは、大阪府泉南市教育委員会の岡一彦さんだ。
発掘された「瓦漏」を見せていただくために泉南市を訪ねた。泉南市は和歌山県のすぐ近くなので、東京より暖かい。暖かい地で生育するさとうきびには、適した地だと実感できる。
大阪府の南部、泉州地域に位置する泉南市の幡代遺跡は、平安時代後期・室町時代・江戸時代の3期の盛期が確認されている遺跡である。
平成5 (1993)年の発掘調査では、18世紀後半から19世紀前期の廃棄土坑から、多くの陶磁器や瓦などが発掘された。その中に、植木鉢のように底に穴の開いた遺物を見つけたのだった。(『泉南市文化財年報 No.1』(1995年))
「これはなんだろう・・・」。岡さんは、規格的で、大きさが決められており、また、底に開けられている穴は、容器を焼く前に意図的に開けられていたことなどから、産業で使われたものではないかと考えた。そこで、パラパラと民具や道具の絵を載せた本をめくっていた時に、砂糖生産用の道具に、植木鉢のように底に穴のあいた容器の絵を見つけたのである。
しかし、これだけでは、これまで紹介してきたような、植木鉢のように底に穴の開いた分蜜容器である「瓦漏」とは、断定しがたい。それを裏付けたのは、江戸時代の後期にこの泉州では、砂糖生産が行われていたことを記す文字史料だった。
江戸時代の農学者である大蔵永常も泉州での砂糖製法を見たことを、文政年間前期(1817年〜)にはその大綱が出来上がっていたと考えられる『甘蔗大成』の中で記している。また、泉州の地方文書にも、天保12(1841)年以降ではあるが、砂糖製造を示す史料がいくつか見つかっている。
その後の発掘でも、同遺跡から「瓦漏」が出土し、平成10(1998)年から始まった泉南市の男里遺跡からも、同様の「瓦漏」が多数出土した。特に男里遺跡に含まれる光平寺跡から出土した「瓦漏」には、底部に2文字の刻印が認められ、最初の字は「瓦」と読める。下の字が判読不明であるが、「『漏』という字だったらいいのに・・・」と、岡さんと私。う〜ん、やっぱり判読不明。写真1〜3は、泉南市教育委員会のご協力を得て撮影させていただいた。日本で出土した「瓦漏」を見るのは初めてなので、感激はひとしおだった。



また近隣の阪南市や泉佐野市、また和歌山県御坊市でも同様の「瓦漏」が出土している。
岡さんが、「瓦漏」では?と着想される以前は、底に穴が開いていて、植木鉢に酷似しているため、砂糖製造とは結びつけることなく見逃されてきた可能性もあるのが残念である。
土の中に埋もれた遺物からのアプローチによる砂糖の歴史研究は、20世紀の終わりに新たな幕が上がったばかりである。「瓦漏」がどんどん発掘されれば、日本での産地の特定や「瓦漏」を使用した砂糖の生産実態など、新たな発見が期待できる。
しかし、本連載第1回目(2011年3月号)で紹介したように、現在日本で行われている伝統的な砂糖製造法では、「瓦漏」を使用した分蜜法とは全く異なり、醤油や酒をてこの原理で加圧する「押し船」を使用して、蜜を強制的に押し出して分蜜する「加圧法」が採られている。
簡易な加圧法については、すでに明和年間に、武蔵国の名主、池上太郎左衛門が、田沼意次や関東郡代の伊奈半左衛門のもとで試作披露を行った際に、少量ではあるが「搾る」「押し付ける」という分蜜法を採っていたことを2012年6月号で書いた。
「押し船」などの加圧器具は、享和元(1801)年に記された讃州での砂糖製法の聞き書き『砂糖の製法扣』 (ケンショク「食」資料室蔵)に、粘りがあって蜜(モラセス)を取り除くことが出来ないときに使用すると記されている。
また同時期の別の史料によると、「加圧法」を採ったと考えられる砂糖は、砂糖製造を行う家では艶が抜けるので「下品」とされていた。したがって、「覆土法」によって作られた砂糖は「上品」であったと考えられるのである。
明治6(1873)年の「糖製一覧」には、押し船による砂糖製造法の絵が記されている。現在の「和三盆」製造と同じ「加圧法」による分蜜法だ(写真4)。
岡さんが、「瓦漏」では?と着想される以前は、底に穴が開いていて、植木鉢に酷似しているため、砂糖製造とは結びつけることなく見逃されてきた可能性もあるのが残念である。
土の中に埋もれた遺物からのアプローチによる砂糖の歴史研究は、20世紀の終わりに新たな幕が上がったばかりである。「瓦漏」がどんどん発掘されれば、日本での産地の特定や「瓦漏」を使用した砂糖の生産実態など、新たな発見が期待できる。
しかし、本連載第1回目(2011年3月号)で紹介したように、現在日本で行われている伝統的な砂糖製造法では、「瓦漏」を使用した分蜜法とは全く異なり、醤油や酒をてこの原理で加圧する「押し船」を使用して、蜜を強制的に押し出して分蜜する「加圧法」が採られている。
簡易な加圧法については、すでに明和年間に、武蔵国の名主、池上太郎左衛門が、田沼意次や関東郡代の伊奈半左衛門のもとで試作披露を行った際に、少量ではあるが「搾る」「押し付ける」という分蜜法を採っていたことを2012年6月号で書いた。
「押し船」などの加圧器具は、享和元(1801)年に記された讃州での砂糖製法の聞き書き『砂糖の製法扣
また同時期の別の史料によると、「加圧法」を採ったと考えられる砂糖は、砂糖製造を行う家では艶が抜けるので「下品」とされていた。したがって、「覆土法」によって作られた砂糖は「上品」であったと考えられるのである。
明治6(1873)年の「糖製一覧」には、押し船による砂糖製造法の絵が記されている。現在の「和三盆」製造と同じ「加圧法」による分蜜法だ(写真4)。
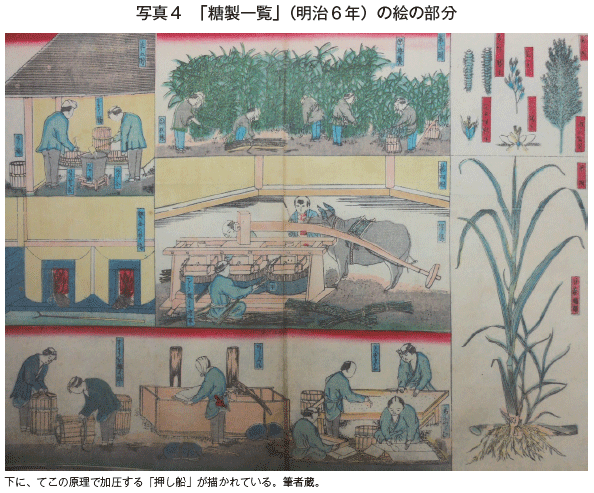
ではなぜ、吉宗の頃から研究・実践していた「覆土法」による分蜜が、「加圧法」に取って代わられてしまったのであろうか?
それは、酒や醤油作りに使用する、てこの原理で加圧する「押し船」という器具が、すでに日本にあって身近であったことが大きな理由であろう。「瓦漏」を使用して、その後、覆土を行う方法だと、最低2週間は必要だ。「加圧法」だと、どのくらい白くするかの度合いによるが、丸一日から5日くらいですむ。「効率」を考えれば、「覆土法」よりもはるかに「加圧法」の方が優位である。
そして、さとうきびの状態や、煮詰め過ぎなどによって、モラセスに粘りがあって重力で蜜が下に落ちない時は、分蜜するのに強制的な圧力が必要となり、この加圧器具は役に立つ。
興味深い報告がある。
八百啓介氏の「一八世紀出島オランダ商館の砂糖貿易」『近世オランダ貿易と鎖国』250−254頁によれば、1700年前後のオランダ船が輸入した白糖には、Cabessa(上白糖)、Halve Cabessa(中白糖)、 Bariga(下白糖)の3種の等級があり、長崎出島での取引価格は、下白糖が一番高く、また、仕入れ高から算出した利益率でも下白糖が一番高かったという。さらに、粗糖(Muscovade)も輸入しており、その利益率は、上白糖の2倍以上でああったとされている。
「砂糖は白い方が高い」あるいは「精製されればされるほど高い」という認識は、日本には通用しなかったようだ。ヨーロッパ人にとっては、さぞかし、大きな驚きだったに違いない。まだ分蜜が進んでいない粗糖や、下白糖の値段の方が高く、さらに利益率も上となれば、こんなに笑いが止まらない商売もないだろう。
鎖国以前のポルトガル貿易でも、日本人の嗜好を示す文章が見つかっている。岩生成一氏の「江戸時代の砂糖貿易について」『日本学士院紀要』第31巻第1号、2頁によると、日本でヨーロッパ国として初めて日本貿易を展開したポルトガルが、マカオで日本へ舶載するために購入した黒砂糖は、白砂糖のよりも価格が安いにもかかわらず、日本では白砂糖よりも高く売れたという。しかもその販売価格は、白砂糖が仕入れ値の2〜3倍であるのに対して、黒砂糖は何と10倍にもなったという。そして、白砂糖の需要はほとんどなく、日本人はむしろ黒砂糖を好むと記されている。
黒砂糖、そして、蜜分が残る粗糖や下白糖の方が高く売れるというデータは、ショ糖だけのすっきりした甘さよりも、蜜分を含んだ甘さを好む、16世紀後半から続く日本人の嗜好を示しているといえないだろうか。
そしてそれは、現在の「和三盆」のようにうっすらと蜜が残る「加圧法」が支持された理由でもあったのではないかと、私は考えている。
それは、酒や醤油作りに使用する、てこの原理で加圧する「押し船」という器具が、すでに日本にあって身近であったことが大きな理由であろう。「瓦漏」を使用して、その後、覆土を行う方法だと、最低2週間は必要だ。「加圧法」だと、どのくらい白くするかの度合いによるが、丸一日から5日くらいですむ。「効率」を考えれば、「覆土法」よりもはるかに「加圧法」の方が優位である。
そして、さとうきびの状態や、煮詰め過ぎなどによって、モラセスに粘りがあって重力で蜜が下に落ちない時は、分蜜するのに強制的な圧力が必要となり、この加圧器具は役に立つ。
興味深い報告がある。
八百啓介氏の「一八世紀出島オランダ商館の砂糖貿易」『近世オランダ貿易と鎖国』250−254頁によれば、1700年前後のオランダ船が輸入した白糖には、Cabessa(上白糖)、Halve Cabessa(中白糖)、 Bariga(下白糖)の3種の等級があり、長崎出島での取引価格は、下白糖が一番高く、また、仕入れ高から算出した利益率でも下白糖が一番高かったという。さらに、粗糖(Muscovade)も輸入しており、その利益率は、上白糖の2倍以上でああったとされている。
「砂糖は白い方が高い」あるいは「精製されればされるほど高い」という認識は、日本には通用しなかったようだ。ヨーロッパ人にとっては、さぞかし、大きな驚きだったに違いない。まだ分蜜が進んでいない粗糖や、下白糖の値段の方が高く、さらに利益率も上となれば、こんなに笑いが止まらない商売もないだろう。
鎖国以前のポルトガル貿易でも、日本人の嗜好を示す文章が見つかっている。岩生成一氏の「江戸時代の砂糖貿易について」『日本学士院紀要』第31巻第1号、2頁によると、日本でヨーロッパ国として初めて日本貿易を展開したポルトガルが、マカオで日本へ舶載するために購入した黒砂糖は、白砂糖のよりも価格が安いにもかかわらず、日本では白砂糖よりも高く売れたという。しかもその販売価格は、白砂糖が仕入れ値の2〜3倍であるのに対して、黒砂糖は何と10倍にもなったという。そして、白砂糖の需要はほとんどなく、日本人はむしろ黒砂糖を好むと記されている。
黒砂糖、そして、蜜分が残る粗糖や下白糖の方が高く売れるというデータは、ショ糖だけのすっきりした甘さよりも、蜜分を含んだ甘さを好む、16世紀後半から続く日本人の嗜好を示しているといえないだろうか。
そしてそれは、現在の「和三盆」のようにうっすらと蜜が残る「加圧法」が支持された理由でもあったのではないかと、私は考えている。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-8678